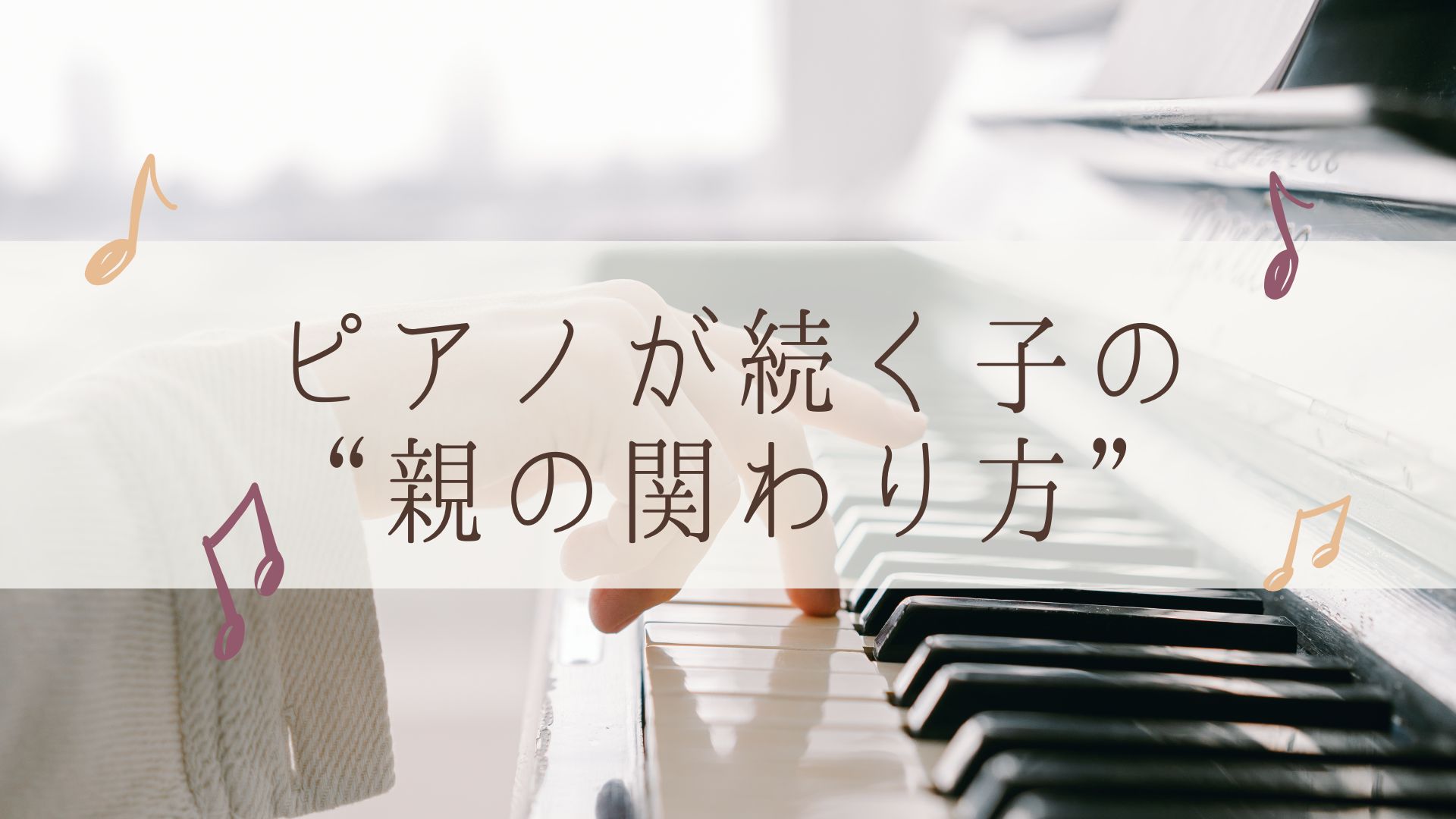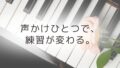ピアノが“続く子”に共通する、親の関わり方5つ
「やりなさい」を言わなくても続く家庭には、“信じて待つリズム”がある。
ピアノを習い始めた当初は、目を輝かせて練習していたのに、
数ヶ月たつと「練習いや」「やめたい」と言い出す・・・。
そんな経験をお持ちの親御さんは少なくありません。
でも実は、「やめたい」という気持ちが出てくるのは、
子どもの“成長のサイン”でもあります。
ピアノを習う中で、子どもたちは日々、
できる・できない、楽しい・つまずく・・・そんな小さな揺れを感じています。
その揺れをどう受け止めるかで、“続く力”は大きく変わります。
この記事では、25年以上の指導経験から見えてきた
ピアノが自然と続く子に共通する【親の関わり方5つ】をお伝えします。
今日からすぐにご家庭で取り入れられる、小さなヒントばかりです。
ピアノを「親の目線」でなく「子どものリズム」で見る
親が“上達”を見たいとき、子どもは“楽しさ”を感じたい
親御さんがつい求めてしまうのは「弾けるようになった?」という“結果”。
一方、子どもが感じている大切なポイントは、
「今日、楽しかったかどうか」です。
楽しさは、練習を続けるうえで最大のエネルギー源。
大人が上達のスピードにばかり目を向けると、
その“楽しさ”が見えづらくなってしまうことがあります。
焦るより、いまのテンポを信じて見守ることが“継続の土台”になる
長く続く子ほど、
「その子自身のテンポ」で成長しています。
速く成長する子もいれば、ゆっくり味わうように進む子もいます。
どちらも、その子にとって自然なペース。
親が焦りを手放して“その子のテンポ”を信じられたとき、
子どもは安心してピアノと向き合えるようになります。
✧˙⁎⋆もし「上達が遅いのでは…」と感じているなら、
そのときこそ大切にしたい視点があります。
ピアノの上達が“遅い”と感じるときに大切なこと 〜親の不安と、講師との上手なつき合い方
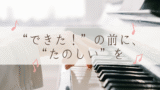
“練習した?”よりも、“今日はどんな音が出た?”
「量」ではなく「質」に意識を向ける声かけ
「練習した?」と聞くと、どうしても“どれだけ弾いたか”という量に目が向きます。
けれど、ピアノが上達するのは量よりも“どう弾いたか(質)”のほうです。
なぜなら、ピアノは 脳が“正しい動きと音”を覚えたときに伸びる楽器だから。
ただ回数だけをこなすよりも、
- ゆっくり丁寧に弾く
- 出ている音をよく聴く
- 指や手首の感覚を感じる
こうした“質のいい数分間”のほうが、上達の回路が太くなります。
だからこそ、声かけも量を問うより、
「今日はどんな音が出た?」と“音の感覚”に意識を向けるほうが効果的。
音を聴く習慣がつくと、
子どもは 自分で気づき、成長できる子 へと育っていきます。
“聴いてもらえる安心感”が、練習のエネルギーを生む
子どもたちは、「上手だから聴いてほしい」のではありません。
「わたしの音を、受け止めてもらえる」安心感を求めています。
ただ隣で聴いてあげる。
1曲弾き終えたら「いい音が出てたね」と一言伝える。
これだけで、練習は“やらされるもの”から、
“聴いてほしいから弾くもの”へと静かに変わっていきます。
✧˙⁎⋆“聴いてもらえる安心”は、子どもの「やりたい」に火をつけます。
その背景を心理学で解説した記事も置いておきます。
ピアノを“やらされている子”は上達しにくい?|心理学が教える“やりたい気持ち”の力
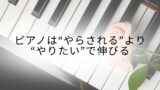
できない日も“信じる目”で見守る
弾かない日にも、心の中では学びが起きている
基本的には、ピアノは“少しでも毎日触れる”ことが上達の近道です。
毎日の練習は、筋肉の記憶も、音の感覚も育ててくれる大切な時間。
これは、25年以上の指導を通して強く感じていることです。
ただし、現実にはどの子にも、
どうしても弾けない日・気持ちが向かない日があります。
そんなときに大切なのは、
「弾けなかった=後退した」ではないと知っておくこと。
脳は、レッスンで得た刺激や、新しく覚えた指の動きを
休息中に“整理して定着させる”力を持っています。
これを脳科学では「オフライン学習」と呼びます。
つまり・・・毎日少しでも触れることが“積み上げ”を作り、
弾けなかった日には“整理と統合”が静かに進む
というふうに、両方が上達のプロセス。
だから、“毎日触れる習慣”を大事にしながら、
弾けない日を必要以上に責めない。
このバランスが、子どものピアノとの関係を長く守るカギになります。
“責めないまなざし”が、ピアノとの関係を守る
「なんで練習しないの?」
「せっかく習ってるのに・・・」
そんな言葉は、知らず知らずのうちに
“ピアノ=責められるもの”というイメージにつながりやすいもの。
できない日を責めないこと。
淡々と信じてあげるまなざしが、子どもにとって大きな支えになります。
・・・そしてもうひとつ。
「できない日」はピアノだけでなく、人生にもありますよね。
そんな日をどう扱うかで、子どもの心の柔らかさは大きく変わります。
✧˙⁎⋆日常の視点から「できない日」をやさしく見つめた記事もあります。
よかったら、息抜きに読んでみてくださいね。
👉 【学校では教わらないシリーズ#04】“できない日”も、人生の一部。
(noteブログにリンクします)
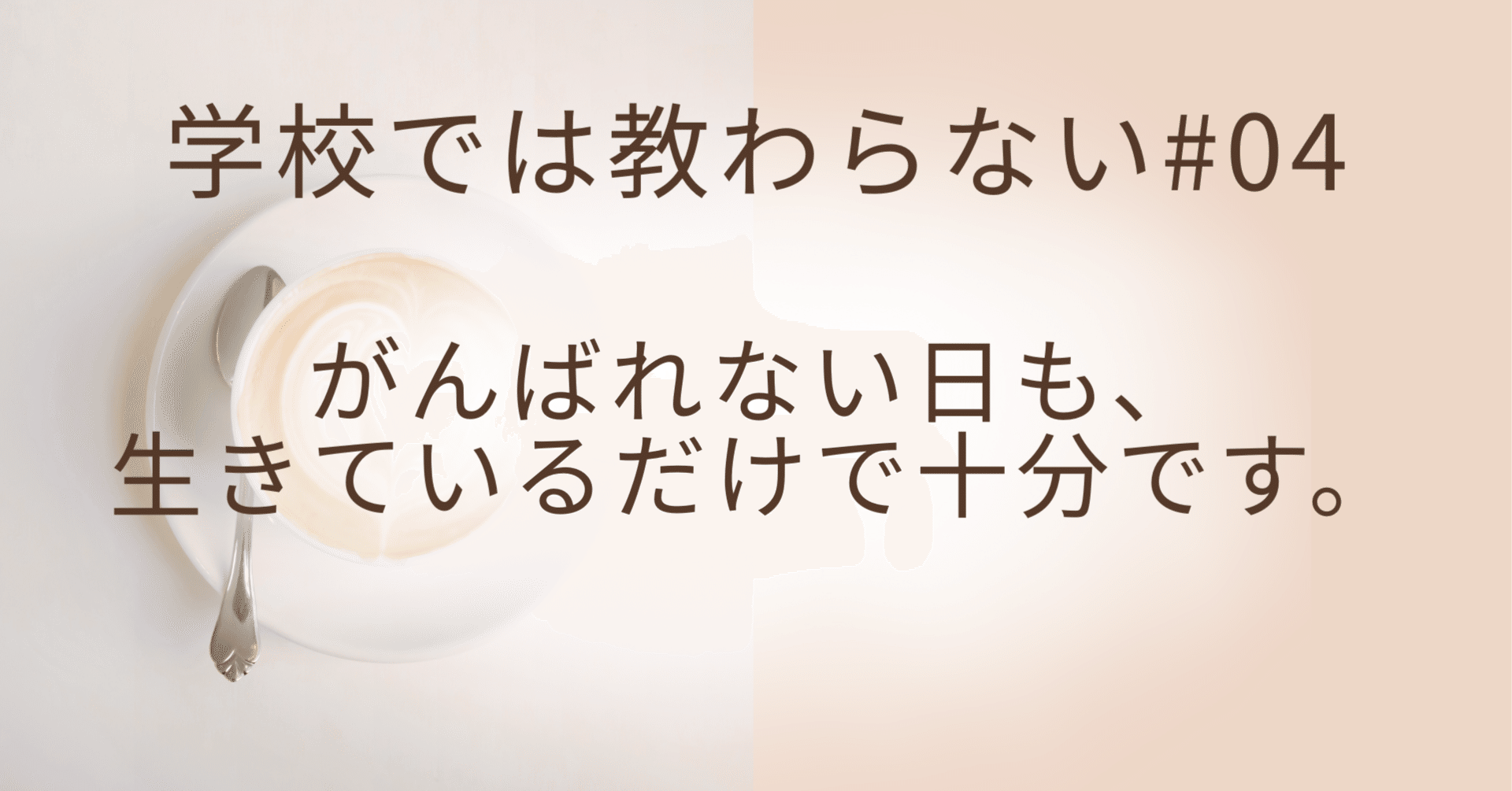
親が焦らない=子どもが安心して挑戦できる
親の不安は、子どもに“空気”で伝わる
「このままで上達するのかな?」
「発表会までに間に合う?」
そんな親の不安は、言葉にしなくても、
子どもには“空気”として伝わります。
不安の空気の中では、子どもは挑戦しづらくなるもの。
反対に、親が穏やかでいると、子どもは自然と挑戦したくなります。
比べる気持ちは“今”の価値を見えにくくする
同じクラスの子、同じ教室の子・・・
どうしても比べてしまうのが親心です。
でも、比べる心が強くなるほど、
目の前の“その子の良さ”が見えにくくなってしまいます。
比べるよりも、「昨日の自分より、ほんの少し前へ」を一緒に喜べる方が
子どもの“続く力”は伸びていきます。
そして、「比べないほうがいい」と頭ではわかっていても、
気づくと他の子と比べてしまう・・・。
それは多くの親御さんがぶつかる、とても自然な揺れです。
✧˙⁎⋆もし、比べぐせをゆるめたいと感じたら、
こちらの記事がヒントになると思います。
👉【学校では教わらないシリーズ #03】比べぐせをゆるめる3つのヒント
(noteブログにリンクします)

比べる視点から、“いま目の前の子ども”に戻るための、実践的な気づきです。
続く家庭には「ピアノが生活の一部」になっている
「勉強→練習→遊び」ではなく、“音がある日常”をつくる
続くご家庭の共通点は、
“ピアノが特別な行事ではなく、日常の一部”になっていること。
時間割のように「勉強の次に練習」と決めるのではなく、
生活のどこかに“ふとピアノがある”状態が自然と生まれています。
- 夕方のひと息タイムに1曲
- 朝の目覚めに音を鳴らす
- 休日のゆるい時間に弾いてみる
音が日常とつながると、練習は義務ではなく“習慣”に変わります。
毎日のリズムに“自然とピアノがある”ことが最大の強み
「続く子」は、やめない子ではありません。
“続けられる環境をもっている子”です。
ピアノが生活のリズムの中に溶け込んでいるご家庭では、
やめたい時期がきても、大きく崩れずにまた戻ってこられる。
その積み重ねが、長い目で見ていちばん力になります。
さいごに
ピアノを続けるうえで、いちばん大切なのは「環境のあたたかさ」です。
叱られて続けたピアノよりも、
見守られて続けたピアノのほうが、
音に“その子らしさ”が宿ります。
焦らず、比較せず、今日の音を聴くこと。
それが、長く続くピアノ時間のいちばんの秘訣です。
上達にはコツがあっても、
子どもの心が育つのは、いつだって“あたたかいまなざし”の中です。
今日できたことも、できなかったことも、
すべてが音楽の一部。
その積み重ねを、これからも大切にしてあげてくださいね。