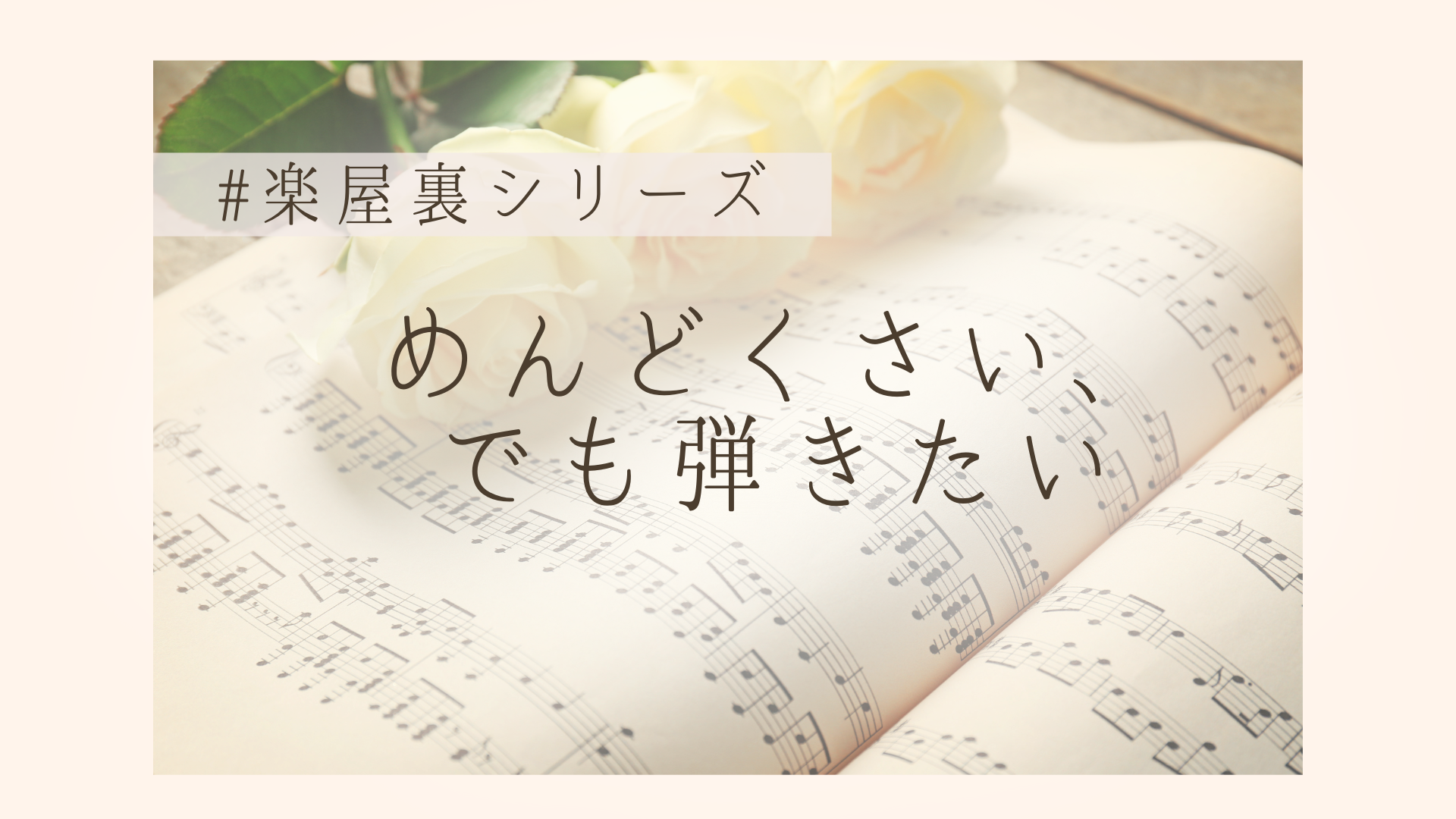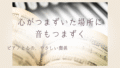ピアノの先生って、いつも弾けるものだと思っていませんか?
実はわたしも、昔はそう思っていました。
でも、教える側になってみて気づいたことがあります。
先生だって、ひそかにコツコツ練習しているんです。
ピアノの先生って、いつ練習してるの?
ピアノの先生って、いつ練習していると思いますか?
生徒さんや親御さんからも、よく聞かれる質問です。
「先生って、もう練習しなくても弾けるんですよね?」
そんなふうに思われることも多いのですが・・・
実は、そんなことないんです。
音楽教室時代のわたしは、レッスン前の午前中に、
できるだけまとまった時間をとって練習していました。
でも、家事や用事で午前が難しい日は、
教室へ早めに行って、生徒さんが来る前の時間や、
レッスンの空き時間を活用して練習していました。
今は教室を離れ、自分のペースで動けるようになったものの、
逆に「今日はこの後〇〇があるから・・・」と後回しになってしまう日もあって。
“時間がある=練習できる”とは限らないんだな・・・
と痛感することもあります(笑)。
昔のわたしは、こんな練習をしていました
学生時代の練習は、今とはまったく違うものでした。
小学生の頃は、毎日2時間くらい。
中学生では1日3時間、高校からは4時間以上が当たり前になっていて、
休日はもっと長く弾いていました。
元旦以外はすべて“練習日”。
今思えば、完全なる体育会系です(笑)。
大学に入ってからは、講義のスケジュールによって練習時間も前後しましたが、
空いている時間はとにかく練習室へ。
1日に4〜5時間、多い日はもっと。
特に試験前は、お昼を食べるのを忘れてしまうほど没頭していたこともあります。
・・・と、ここまで読むと「練習が大好きだったんですね!」と
思われるかもしれませんが、実はそうでもありません。
練習は、あまり好きではありませんでした。
ほんとうに、めんどくさいなあ・・・とよく思っていました。
やっても思うように弾けない日も多くて、悔しくて、しんどくて・・・。
先生から出される課題をきちんとこなしていくこと・・・
これがもはやタスクになっていたと言ってもいいくらい。
それでも、辞めなかったのは、
ピアノを弾くことが、やっぱり好きだったからです。
練習は嫌いでも、音楽が鳴り始めた瞬間に、
すべてが報われる気がしていました。
音と向き合うことで、いつも救われていた気がします。
いま、挑戦しているのはこの曲です
そんなわたしが、いま向き合っているのが、バロック音楽。
主にバッハを弾いています。
というのも、わたしがこれまで師事してきた先生方は、
バロックをレッスンで多く取り上げるタイプではありませんでした。
子どもの頃にインベンションや平均律はひととおり学びましたが、
それ以外はあまり深く触れてこなかったのです。
講師になってしばらく経った頃、
ある先生がふとおっしゃった言葉が、ずっと心に残っています。
「バロック音楽を、ロマン派のように弾いてみたらどうなると思う?」
そのときの衝撃といったら・・・。
“バロックは淡々と、様式美を守って弾くもの”というわたしの固定観念が、
一気に崩れた瞬間でした。
それ以来、バロック音楽の奥深さに惹かれるようになり、
「もっと自由に、もっと自分らしく表現してみたい」と思うようになりました。
だからいま、誰に見せるわけでもなく、自分のために練習しています。
生徒さんにも時々、こんな表現もできるんじゃないかな、とアドバイスすることも。
何度も繰り返し弾いて、やっとバッハの面白さが、ほんの少しだけ見えてきた気がします。
教えることと、弾くことは別物かもしれない
ピアノ講師として何年か経った頃、
ふと気づいたことがありました。
最初のうちは、自分が習ってきた時の言葉をそのまま使って、
生徒にも同じように伝えていたんです。
でも、ある日ふと、「あれ?」と思ったんですよね。
同じように説明しているのに、わかってくれる子と、全然伝わらない子がいる。
そのときにようやく、「教える」って、ただ言うことじゃなくて、
“伝わるように工夫する”ことなんだなって気づいたんです。
そんな気づきがあってからは、生徒さんがいま置かれている環境や、性格、目標、
すべてに合わせて言葉や進め方を工夫をしています。
同じ教材でも、声かけが変われば、子どもの反応もガラリと変わるんです。
そして何より、子どもたちの「わかった!」という表情に、
わたし自身がいつも教えられている気がします。
先生は、完成された存在ではなくて、
いまも学びの途中にいる、ひとりの“音楽好き”なんです。
これからもきっと、指先と心を通して、音と向き合い続けていくんだろうな・・・と思っています。
あとがきにひとこと
最後まで読んでくださってありがとうございます。
ピアノが好きな方、教える立場の方、そして、ただ音楽が好きなあなたへ。
またこんな“楽屋裏”も、少しずつ綴っていけたらと思っています。