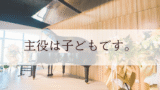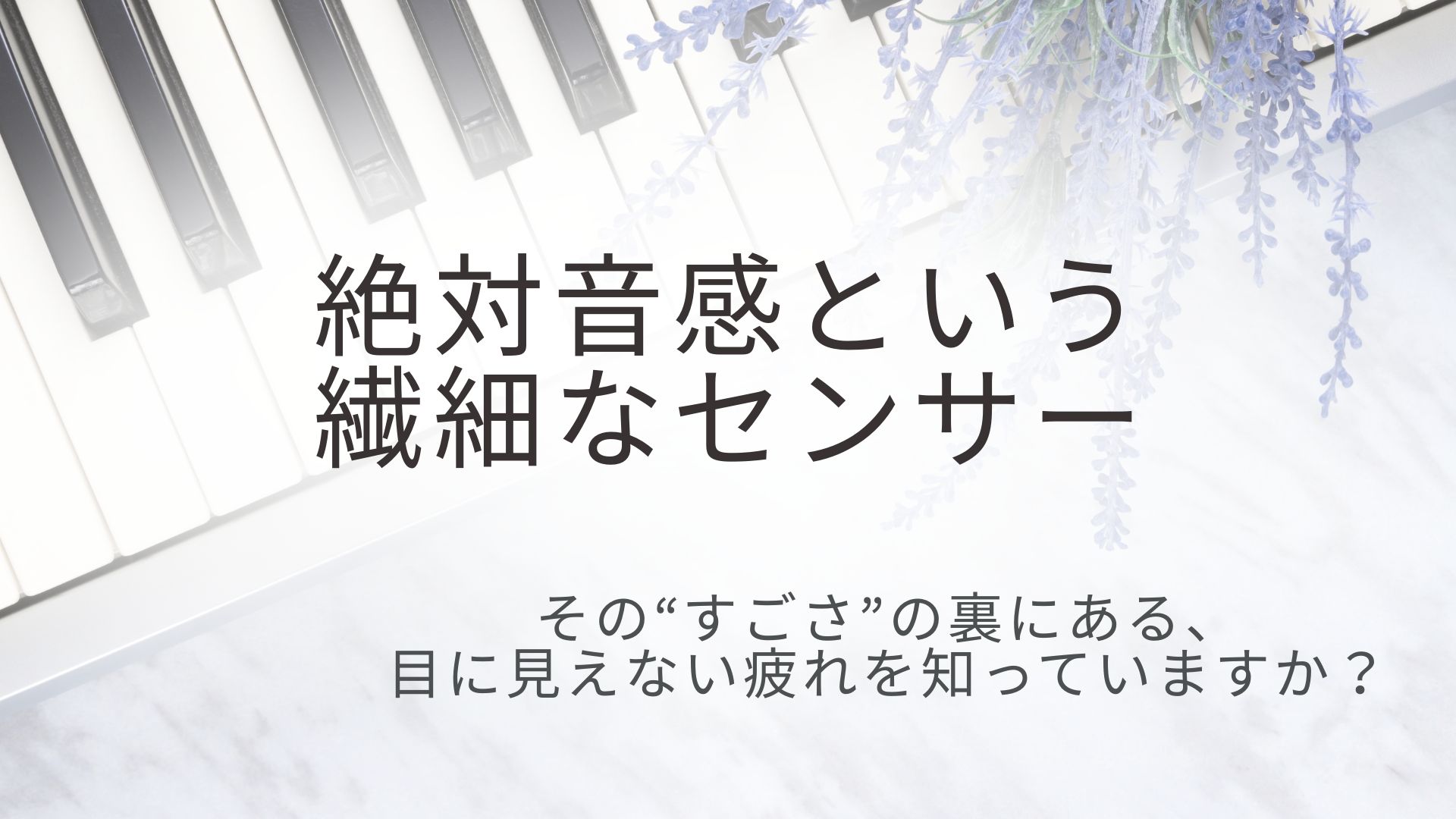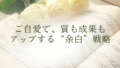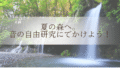絶対音感って必要?
絶対音感って、本当に必要なんでしょうか?
長年ピアノを教えてきた経験と、
私自身の感覚を含めて、
今回はそのことについてお話ししていきたいと思います。
絶対音感はつけるべき?親として考えておきたい視点
「うちの子に絶対音感を身につけさせたいんです」
ピアノのレッスンをしていて、そんな声をよく耳にしました。
たしかに、絶対音感は“特別な才能”のように思えるかもしれません。
実際に音楽の世界で生きていくなら、役に立つ場面はたくさんあります。
でも私は、自分自身が絶対音感を持っているからこそ、
「それって本当に必要?」と感じることもあるのです。
もちろん絶対音感があることで、助けられたこともあります。
けれど同時に、日常生活でちょっとしんどくなる場面もありました。
この記事では、「絶対音感はすごいもの」というイメージとは少し違う、
“音に敏感な子どもたち”の視点をお届けできたらと思います。
絶対音感を持つことのメリット・デメリットを、
いちどフラットに考えてみませんか?
絶対音感と相対音感の違いとは?簡単にわかる音感の基礎知識
まず、「絶対音感」ってどういうものなのでしょうか?
簡単に言えば、ある音を聞いたときに、
それが何の音(音名)かがすぐにわかる力のことです。
たとえば、ピアノで「ド」の音が鳴ると、「これはド」と瞬時に判断できる。
音を聞いた瞬間に、頭の中で音名が“浮かんでくる”ような感覚です。
これは訓練によって、特に幼児期に身につけやすいとされています。
早いうちから毎日同じ音に触れることで、
自然と音を覚えていく、というやり方ですね。
一方で、「相対音感」というものもあります。
これは、ある基準の音からの“間隔”によって他の音を判断する力。
たとえば、「今の音はドだった。
じゃあ、次に鳴ったのはそこからひとつ上がったからレだな」
といったように、音と音の関係性から音を聞き取る力です。
実は、相対音感のほうが音楽の流れや調性を感じるうえではとても役立つこともあります。
絶対音感がなくても、音楽を深く楽しんだり演奏したりすることは十分に可能です。
実はつらい?絶対音感を持つ子どもが抱える繊細な悩み
絶対音感があると、「音を聴き分けられる力が高い=音楽に向いている」と思われがちですが、
実際には日常生活のなかで思わぬ“しんどさ”を感じる場面もあります。
たとえば、駅のホームで鳴るチャイム、
家電の「ピーピー」「チン」といった電子音・・・。
これらがただの“効果音”ではなく、
音名付きのメロディとして頭に飛び込んできます。
しかもそのメロディが、微妙に不協和音だったり、
耳につく高さだったりすると、
無意識のうちにセンサーが反応してしまって、
知らないうちに疲れてしまうんです。
印象的だったのは、お風呂が沸いたときのメロディ。
クラシックの有名なフレーズが流れてきたのですが、
電子音で再現されていたために、音程がズレていて不協和音になっており、
わたしの脳のセンサーが“これはおかしい”と反応してしまったんですね。
「この曲、知ってるけど・・・なんか変?」と
違和感の理由がわからず、最初は戸惑ったほどです。
また、カラオケでも似たような経験があります。
原曲よりキーを上げたり下げたりして歌っている人の声を聞くと、
曲の“調性”が変わることにセンサーが反応してしまい、
原曲とはまったく違う雰囲気に感じてしまうんです。
もちろん、それが悪いことだとは思いません。
その人にとって歌いやすいキーで歌うのは自然なこと。
でも、絶対音感を持っていると、
細かい音のニュアンスや色合いの変化まで拾ってしまう
“高感度のセンサー”が働いてしまうために、
「なんだかしっくりこない」と感じることがよくあるんです。
周囲は気にしていないのに、自分だけが音に反応してしまう。
そんな“センサーの感度が高すぎる”状態は、
ときに神経の疲れや孤独感につながることもありました。
音楽をするうえではとても便利な力なのに、
日常ではちょっと過敏すぎるセンサーになってしまう。
それが、絶対音感の裏側にある現実なのかもしれません。
音に振り回されない心のコツ〜センサーとのつきあい方
そんなふうに、絶対音感によって日常の音に疲れてしまうこともありましたが、
今ではだいぶラクに過ごせるようになってきました。
それは、「音に反応しないように無理やり我慢している」わけではなく、
自分の中の感覚をうまく扱えるようになってきたからだと思います。
昔の私は、音が鳴るたびに無意識で反応し、
まるで高感度のセンサーが作動しっぱなしのような状態でした。
でも今は、「あ、この音は気になるな」と
少し距離をとって観察できるようになったことで、
そのまま受け流すこともできるようになりました。
すべての音に巻き込まれるのではなく、
必要なものだけをキャッチして、
あとはスルーする力が少しずつ育ってきた気がします。
この“ちょうどよい距離感”がとれるようになってからは、
日常の中にある音の世界も、
ずいぶんと穏やかに感じられるようになりました。
絶対音感より大切なのは、センサーとの“距離感”かもしれません
絶対音感は、たしかに特別な能力です。
音楽を学ぶうえで助けになる場面も多く、
私自身も恩恵を感じたことがあります。
でも同時に、それは「音に対するセンサーがとても繊細で鋭い」ということでもあるのです。
周りが気にしていない音に反応してしまったり、
ちょっとしたズレが気になったり・・・
そのセンサーが高感度であるがゆえに、
日常で疲れやすくなることもあります。
私が今伝えたいのは、「絶対音感をつけるべきかどうか」ではなく、
“そのセンサーとどう付き合っていくか”を
大切にしてほしいということです。
もしお子さんが音に敏感だったとしても、
それを「すごいね」と肯定してあげながら、
「疲れていないかな?」「気にしすぎていないかな?」と、
そっと気にかけてあげてほしいのです。
高性能なセンサーを持っているということは、
世界を豊かに、細やかに感じとる力があるということ。
そのセンサーを無理に鈍くするのではなく、
ちょうどいい距離で、心地よく使っていけるように見守ってあげられたら・・・
きっと、その子の感性はのびやかに育っていくはずです。
🎵合わせて読みたい記事
🎹【第2弾】絶対音感の“すごさ”は、子どもにとってどんな恩恵になるのでしょうか。
音楽を長く続けるために、本当に役立つ視点をまとめました。
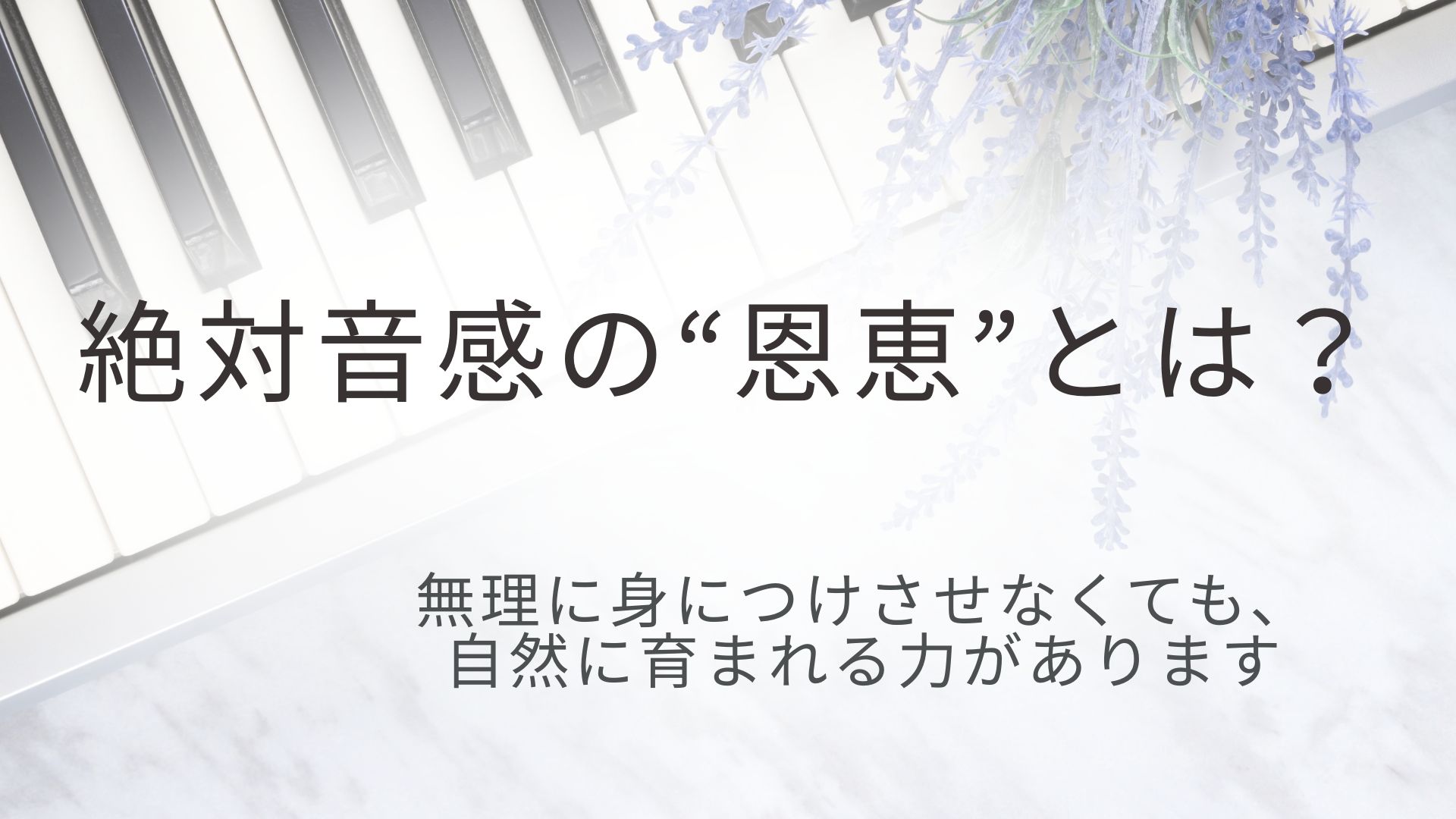
🎹「子どもの晴れ舞台で、親が試されていること」
発表会やコンクールなど、大切な本番で意外と試されるのは子どもの力だけではなく、親の関わり方。
親の緊張や期待が、子どもにどう影響するのかを考えます。