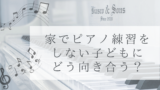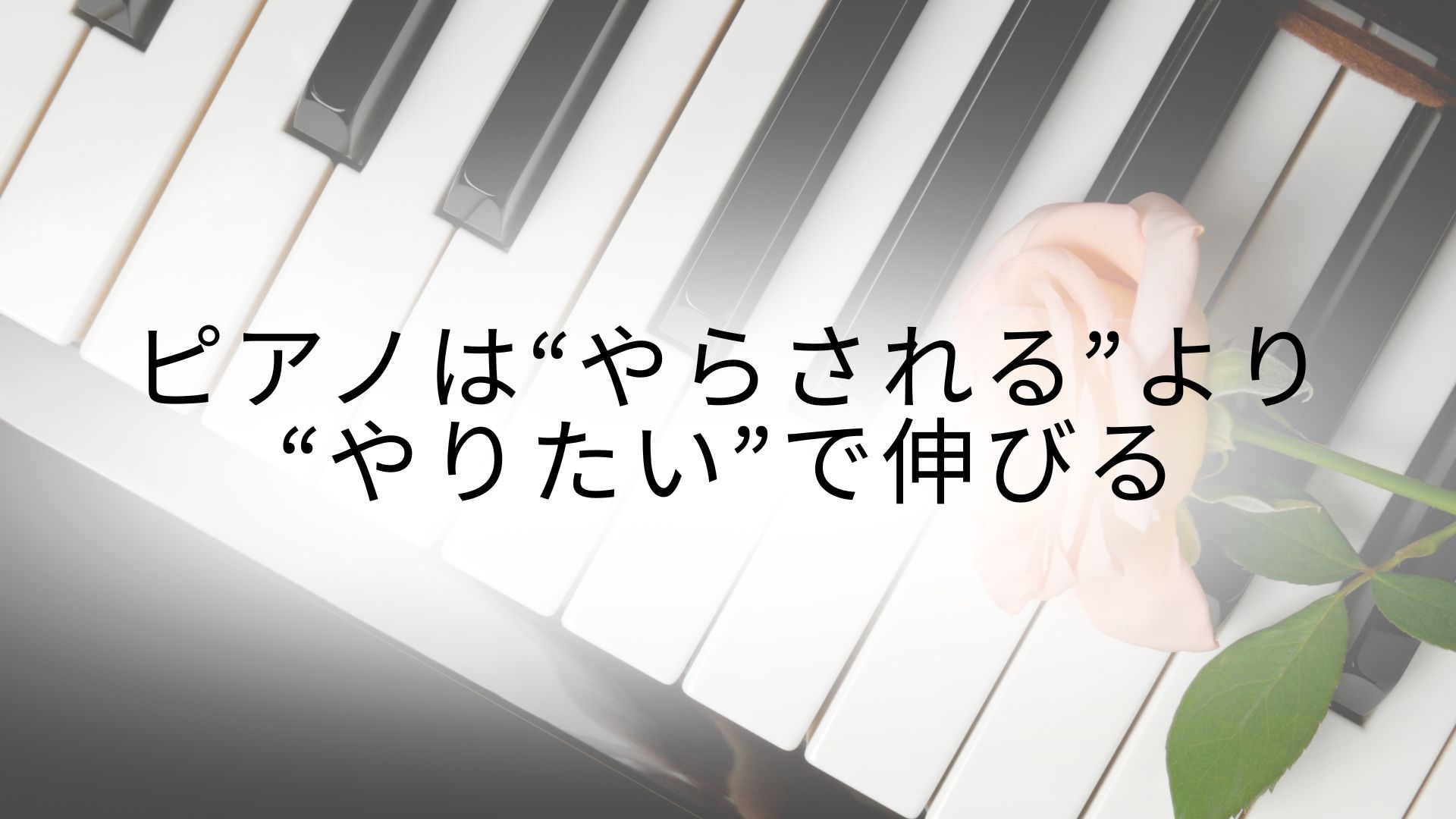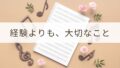ピアノを“やらされている子”は上達しにくい?
ピアノを習っている子どもの中には、「自分の意思で習っている」というより、
親のすすめで始めた子も少なくありません。
そういった子は、レッスンでも特徴がはっきりと表れることがあります。
練習してこない。
少し難しいところに出会うと、すぐに「無理」と言う。
モチベーションが低く、レッスンに前向きな姿勢を見せない。
講師として見ていると、「やらされている子」と「自分からやりたい子」では、
明らかに進度も曲の仕上がりも違うのです。
これは、決してピアノだけの話ではありません。
勉強でも、部活でも、仕事でも──
「やらなければ…」という気持ちだけでは続きにくく、
成果にもつながりにくい。
一方で「やりたい!」と思って取り組んでいる人は、
上達のスピードも伸びやかで、楽しさを伴って成長していきます。
「やらされ感」で習う子の特徴
「やらされ感」でピアノを習っている子どもには、いくつか共通する特徴があります。
1. 練習に身が入らない
家での練習がほとんど進んでいません。
譜読みが途中で止まっていたり、宿題の曲が1週間前とまったく同じ状態で残っていたりします。
もちろん「忙しかったのかもしれない」と思うこともありますが、
何週も続くとなると、やはり“自分からやりたい気持ち”が薄いのだと感じざるを得ません。
2. 難しい部分を避ける
少しでも難しいところに出会うと、すぐに「できない」「無理」と言って、
譜面を閉じたくなってしまう子もいます。
ある生徒さんは、右手と左手を合わせる練習でつまずいたとき、
「もうイヤ!」と楽譜を机に伏せてしまいました。
挑戦を避ける気持ちは誰にでもありますが、
「やらされ感」が強い子ほどその傾向がはっきり出ます。
3. 上達スピードが遅い
自主的に習っている子に比べると、明らかに進度が遅くなりがちです。
新しい曲に入るのも時間がかかり、
発表会の曲が仕上がるまでにずいぶんエネルギーを要します。
一方、「自分から弾きたい!」という気持ちで練習している子は、
難しい曲でも驚くほど早く仕上げてしまうことがあります。
この差は、意欲の有無が大きく影響していると感じます。
4. 曲の完成度も浅い
なんとか最後まで弾けるようにはなるものの、
音楽的な表現や細やかな表情まではたどり着けないことが多いです。
「間違えないこと」がゴールになってしまい、
曲に込められた世界や、自分の思いを表現するまでの余裕がありません。
これは、練習量の不足だけでなく、
「やりたい!」という気持ちが欠けていることが大きいように思います。
このような特徴は、講師としてレッスンを重ねるうちに自然と見えてくるものです。
そして残念ながら、「やらされ感」を抱えたままでは、
音楽の楽しさに触れる前に辞めてしまうケースも少なくありません。
「やらなければ」より「やりたい」で伸びる理由
子どもが本当に伸びていくときには、共通していることがあります。
それは「やらなければ」ではなく、「やりたい」と思って取り組んでいることです。
自己決定理論が示す「やりたい気持ち」の力
心理学の自己決定理論(Self-Determination Theory)では、
人が意欲的に行動し続けるためには「自律性」「有能感」「関係性」の
3つが必要だとされています。
なかでも「自律性」──つまり「自分で選んでやっている」という感覚は、
学びや成長の質を大きく左右します。
「やらされている」と感じている子どもは、
この“自分で選んでいる”という感覚を持ちにくいのです。
そのため、練習に向かう姿勢はどうしても受け身になり、
続ける力が弱くなってしまいます。
内発的動機づけがもたらす集中力と継続力
一方で、「弾いてみたい」「あの曲を仕上げたい」といった内発的動機づけがあるとき、
子どもは自然と集中力を高め、練習を続ける力が湧いてきます。
ちょっと難しいところに出会っても、
あきらめるのではなく「どうすればできるかな?」と工夫する姿勢が出てきます。
この「工夫しながら続けられる力」こそ、上達を支える大切な要素です。
エフィカシー(自己効力感)の育ち方
ここで重要なのが、エフィカシー(自己効力感)です。
エフィカシーとは「自分はできる」と信じられる感覚のこと。
小さな成功体験を積み重ねることで育っていきます。
「やりたい」という気持ちで取り組んでいる子は、
失敗しても「次はできるかも」と前向きに考えやすく、
挑戦を繰り返すうちに自己効力感が自然と高まっていきます。
その結果、さらに大きな挑戦にも立ち向かえるようになり、
上達のスピードも伸びやかになります。
逆に「やらされている」と感じている子は、
失敗を「怒られる」「できない自分」と結びつけやすく、
挑戦そのものを避けるようになりがちです。
これでは自己効力感は育たず、「自分はできない」という思い込みが強化されてしまいます。
「やりたい」が生む成長の循環
「やりたい」という気持ちがあると、
→ 集中力が増す
→ 小さな達成感を得る
→ 自己効力感が育つ
→ さらに挑戦してみたくなる
という、プラスの循環が生まれます。
反対に「やらされ感」は、
→ 受け身で取り組む
→ 失敗すると「やっぱり無理」になる
→ 自己効力感が下がる
→ さらにやりたくなくなる
というマイナスの循環になりやすいのです。
この違いこそが、「やらなければ…」と「やりたい!」で
取り組む子どもたちの上達スピードや仕上がりの差を生んでいるのだと思います。
脳科学から見る「やらされ感」
子どもが「やらされている」と感じながら練習するのと、
「やりたい!」と思って取り組むのとでは、
脳の中で起こっていることがまったく違います。
ドーパミンが「できた!」を強化する
人が「楽しい!」「やってみたい!」と感じたときには、
脳内でドーパミンという神経伝達物質が分泌されます。
ドーパミンは、やる気や集中力を高めるだけでなく、
学習の定着を助ける働きもあります。
「できた!」という達成感と結びついたとき、
脳はその体験を「快」として記憶に残し、次の挑戦への原動力になります。
ピアノの練習でも、「このフレーズ弾けた!」「先生に褒められた!」と感じた瞬間に
ドーパミンが働き、上達のサイクルが回り始めるのです。
コルチゾールが学習を妨げる
一方、「怒られるからやらなきゃ」「仕方なくやっている」という状態が続くと、
脳内ではコルチゾールというストレスホルモンが優位になります。
コルチゾールが高い状態では、集中力が散漫になり、
海馬(記憶を司る部分)の働きも低下します。
その結果、せっかく練習しても身につきにくく、
「やっぱりできない」という悪循環につながってしまうのです。
音楽は「感情 × 記憶 × 運動」の統合活動
ピアノを弾くことは、ただ指を動かすだけではありません。
- 感情を込めて音を表現する
- 楽譜を記憶する
- 指や身体を協調して動かす
このように、感情・記憶・運動が同時に関わる、とても複雑で高度な活動です。
だから、「楽しい!もっとやりたい!」という前向きな感情が伴わなければ、
脳はうまく統合できず、上達もしにくいのです。
つまり、脳科学の視点から見ても、「やらされ感」より「やりたい気持ち」があることが、
ピアノの上達に直結していると言えます。
「やらされ感」を「やりたい」に変える工夫
「やらされ感」でピアノを習っている子どもにとって、
一番の課題は「どうやって練習に自分の気持ちをのせられるか」という点です。
ここでは、親や講師が日常の中で工夫できるポイントをいくつかご紹介します。
小さな達成感を味わわせる
大きな曲をいきなり仕上げるのは大変ですが、
ほんの数小節でも「できた!」と感じられると、子どもの表情はパッと明るくなります。
「ここまで弾けるようになったね」「今日は昨日よりもスムーズだったね」と声をかけることで、
達成感が強化され、次の練習につながります。
小さな成功体験の積み重ねが、
自己効力感(自分はできる!という感覚)を育てる土台になります。
曲や課題を子ども自身に選ばせる
レッスンで与えられる課題の中に、子どもが自分で選べる余地を少し入れることも効果的です。
たとえば「この2曲のうち、どちらを練習してみたい?」と問いかけるだけでも、
子どもの主体性が引き出されます。
自分で選んだ曲には責任感も湧き、「やらされている」から「自分で決めた」に
気持ちが変わっていきます。
「練習しなさい」より「聴かせてほしい」
親御さんの声かけも大切なポイントです。
「練習しなさい!」という言葉は、子どもにとって義務感を強めてしまいがちです。
それよりも「今日の曲、ちょっと聴かせてほしいな」と伝えると、
子どもは「弾いてあげよう」という気持ちでピアノに向かいやすくなります。
練習が「義務」から「共有」に変わることで、
子ども自身のモチベーションも自然と上がっていきます。
評価よりも共感を伝える
子どもが一生懸命弾いたあとに「できたね!」と評価するよりも、
「楽しそうに弾いてたね」「その音、きれいだったね」と
感情に共感する言葉をかけてあげましょう。
評価は「できた/できない」の二択に偏りやすいですが、
共感は子どもの気持ちに寄り添うため、「また弾いてみよう」という
意欲を引き出しやすいのです。
このように、小さな工夫を積み重ねるだけで、
「やらされ感」で始まったピアノが、少しずつ「やりたい気持ち」に変わっていくことがあります。
親や講師がサポート役となり、子どもの気持ちに寄り添いながら場を整えてあげることが、
続ける力を育てる第一歩になります。
まとめ
「やらされ感」でピアノを続けていても、
上達のスピードや曲の完成度には限界があります。
一方で、「やりたい!」という気持ちがある子どもは、
同じ時間を過ごしても驚くほどの伸びを見せます。
ピアノの上達に不可欠なのは、技術だけではありません。
それ以上に大切なのは、「自分でやりたい」と思える心のエネルギーです。
その気持ちを育てるために、親や講師は「やらせる人」ではなく、「やりたい気持ちを引き出すサポート役」でありたいものです。
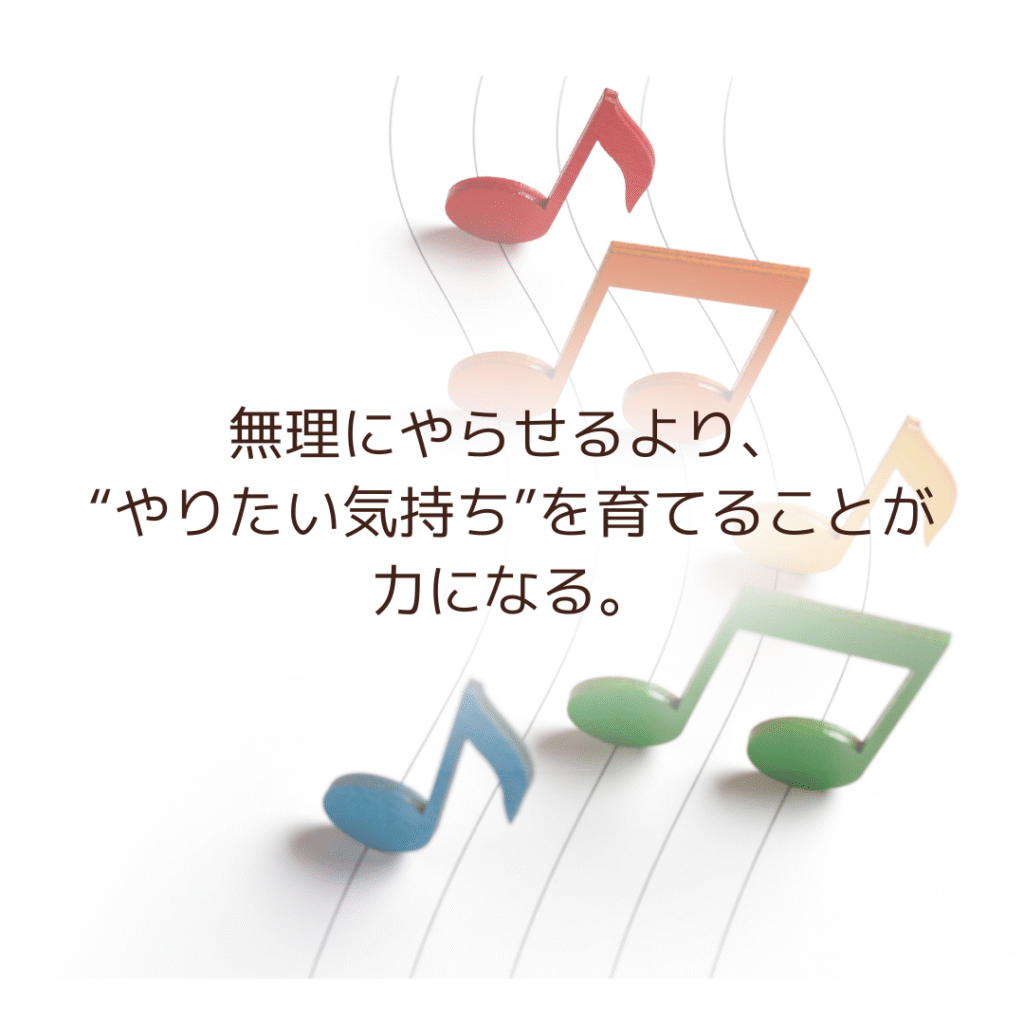
🎵こちらも合わせてどうぞ。
上達していく子には共通の習慣があります。
小さな成功体験が、音楽の未来をどう変えていくのかを解説しています。

「集中力が続かない…」そんなときに親や講師ができる工夫を、
3つの視点からご紹介します。
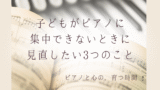
「練習しなさい」と言っても動かない子どもに、どう寄り添えばいいのか。
家庭での関わり方のヒントをまとめています。