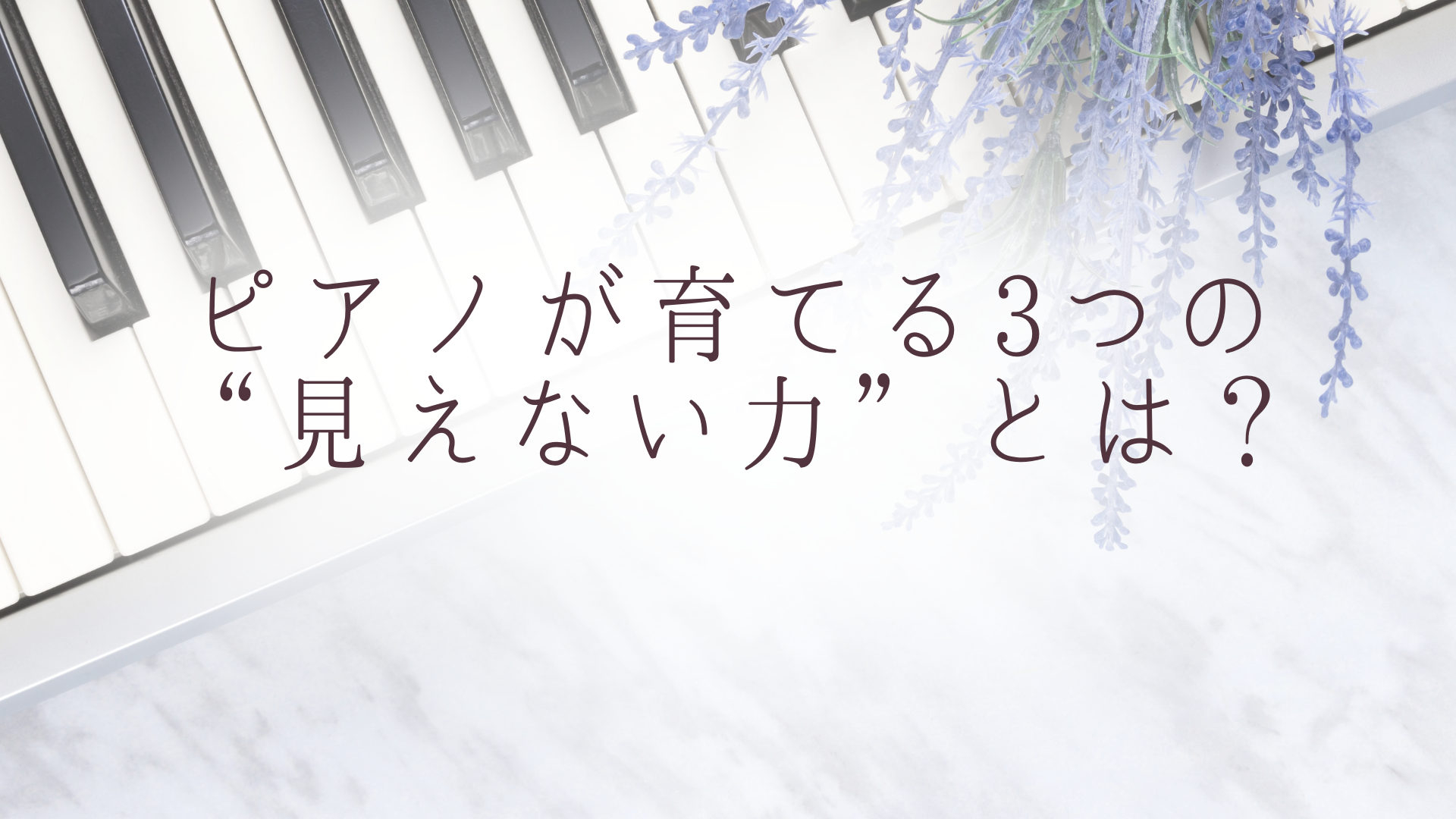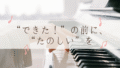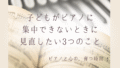ピアノを習うと、どんな力が育つ?非認知能力の視点から見えること
「うちの子、なかなか続かなくて……」
ピアノ講師をしていると、そんな声をよく耳にします。
私は、これまでに25年以上、子どもたちとピアノに向き合ってきました。
日々のレッスンの中で、「すぐに上達すること」よりも、「コツコツと続けていく力」の大切さを何度も感じてきました。
「続ける力」って、最初から備わっているものじゃない。
続ける中で、静かに育っていくものだなぁと。
ピアノは、成果がすぐに目に見えない習いごとです。
何度も同じところを繰り返して、指が覚えてくれるのを待つ。
時には投げ出したくなるような日もあるかもしれません。
それでも、「もう1回やってみようかな」と小さく前を向く。
それを毎週、繰り返していくうちに・・・
子どもたちは、自分でも気づかないうちに「がんばる力」や「集中する力」を育てていくのです。
このように、テストの点数では測れないけれど、人生を豊かにする“見えない力”のことを、教育の世界では「非認知能力」と呼びます。
今日は、ピアノレッスンを通して育まれる、そんな非認知能力について、わたし自身の指導経験から感じてきたことをお伝えできたらと思います。
非認知能力って、なに?
「非認知能力」とは、テストの点数やIQのように数値で測ることができない、“生きる力”のことを指します。
たとえば・・・
・最後までやり抜く力(グリット)
・失敗しても立ち直る力(レジリエンス)
・気持ちをコントロールする力
・自分を信じて進む力
こうした力は、社会に出てからも、人間関係の中でも、長く役立つものです。
教育現場でも注目されており、文部科学省の資料などでも取り上げられています。
ピアノレッスンは、まさにこうした力が自然と育つ場面が多く、私はいつも「音楽って、心の筋トレでもあるな」と感じています。
ピアノレッスンで育まれる“3つの非認知能力”
1.継続力
ピアノは、すぐにできるようになる習いごとではありません。
最初はドから始まり、右手・左手、拍子、小節、強弱・・・と、覚えることがたくさん。
一度に全部は無理なので、少しずつ、でも確実に進めていくしかないんですね。
「昨日より少しできるようになった」
「先週よりスムーズに弾けた」
この小さな積み重ねが、“努力は報われる”という感覚を育てていきます。
これは、大人になってからも大切な“心の財産”になるものだと思っています。
2.集中力
ピアノは、目で譜面を追いながら、耳で音を聴き、手を正確に動かすという、とても高度な集中が求められます。
一見ぼーっとしている子でも、レッスンのときに“ふっ”と集中する瞬間があります。
音の間違いに自分で気づいたり、拍がずれたことに「あれ?」と反応したり。
そういう瞬間が、“集中の芽”だと、私は感じています。
「間違えないように」ではなく、「自分の音を感じながら、丁寧に弾こう」と思えるようになると、集中力は自然に深まっていきます。
3.自己対話・自己調整力
「この指でよかったかな?」
「次、もう少しゆっくり弾いてみようかな」
ピアノの練習は、自分との対話の連続です。
講師が言ったことを受け取って、「そうか、じゃあこうしてみよう」と考え、自分なりにやってみる。
うまくいったらうれしいし、できなかったらまた考える。
この“トライ&エラーの中にある前向きな自己対話”こそが、子どもたちの内面を育てていくのだと感じます。
「結果」よりも「プロセス」を見てあげてほしい
つい、「発表会でうまく弾けた」「コンクールで賞を取った」という“目に見える結果”に目が向きがちです。
でも、その舞台に立つまでに、
何度も指を間違えたり、泣いたり、怒ったりしながら、
「今日もやってみる」をくり返してきた子どもたちがいます。
私は、その目には見えない「がんばった過程」こそが、もっとも尊いと思っています。
すぐに成果が出る子もいれば、じっくり時間をかけて力をためていく子もいます。
“根っこ”が太く育つ子は、実はゆっくり育っていることが多いのです。
まとめ ピアノは、音楽を超えた“心のレッスン”
ピアノレッスンは、ただ音楽を学ぶだけの場ではありません。
音を通して、自分と向き合い、集中し、小さな達成感を積み重ねていく・・・
それは、まるで“心のレッスン”のような時間です。
非認知能力は目に見えませんが、確実に、その子の中に根づいていきます。
音楽の力を信じて、今日もまた、静かに“がんばる力”が育っていく場所。
それが、わたしの思うピアノレッスンの魅力です。