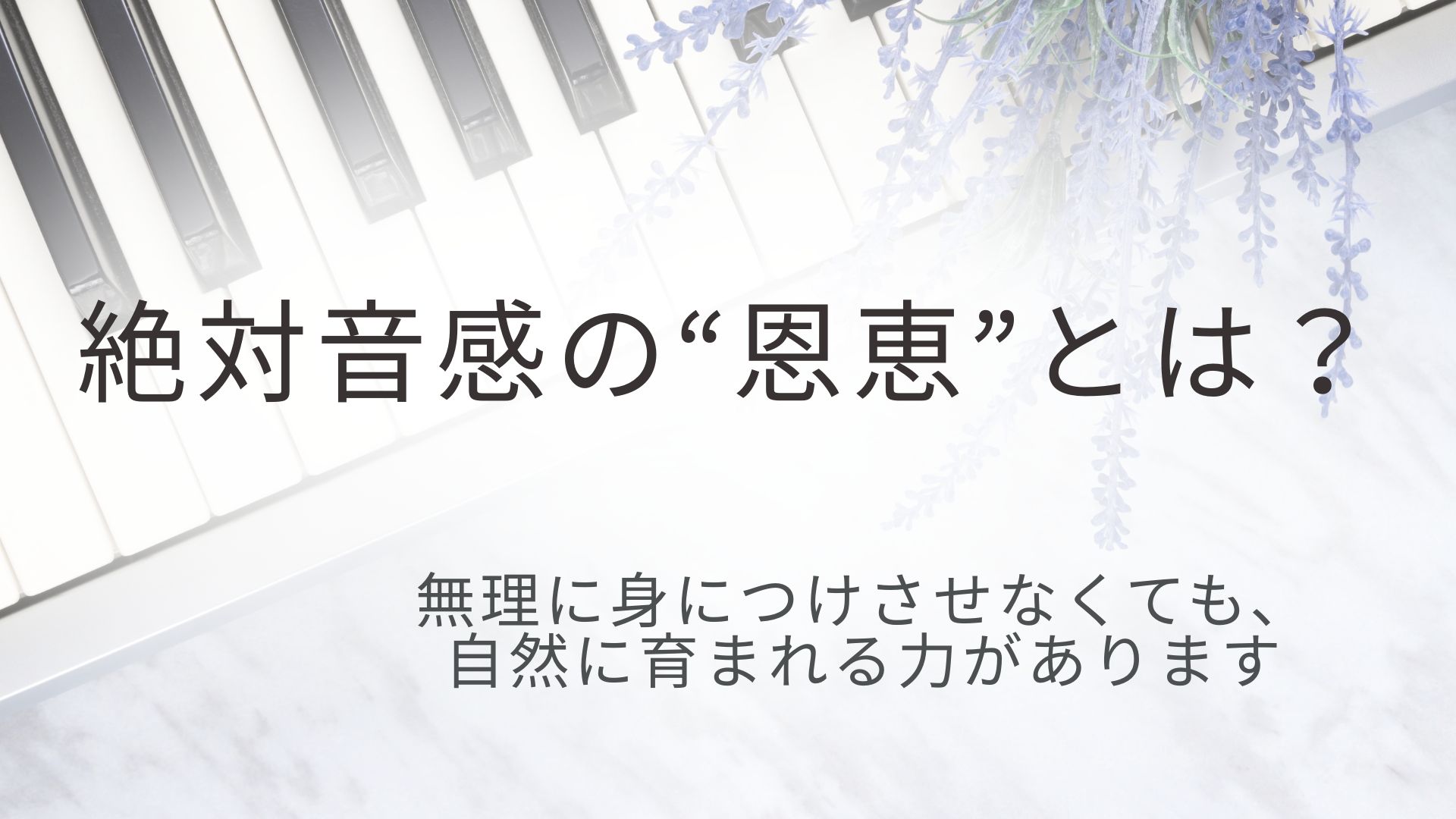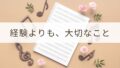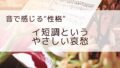絶対音感は必要?音楽を続ける子どもにとっての“恩恵”とは
「先生、うちの子に絶対音感をつけたいんです」
ピアノを習わせる親御さんから、
よくいただくご相談のひとつです。
「絶対音感はあった方がいい」「幼児期にしか身につかない」と聞くと、
“今のうちに絶対につけなくては”
という気持ちになるのも自然なことかもしれません。
けれど、絶対音感は本当に必要なのでしょうか?
メリットばかりに目を向けてしまうと、
知らないうちに子どもの可能性を狭めてしまうこともあります。
この記事では、絶対音感の「恩恵」とされる部分と、
親として気をつけたい視点を整理しながら、
音楽を長く続けていくために
本当に大切なことを考えてみたいと思います。
絶対音感があると、こんなメリットがある
「音楽を聴いただけで、すぐにピアノで弾ける」──
そんな姿を見たら、きっと親としては感動しますよね。
絶対音感を持つ子どもには、
こんな“ちょっと特別な体験”が訪れることがあります。
楽譜がなくても音を再現できる
テレビから流れてきたCMソングや、
保育園で歌った歌。
子どもがピアノに向かい、
耳で聴いた音をそのまま弾きはじめると、
「どうして弾けるの?」と親の方が驚いてしまう瞬間があります。
曲を覚えるスピードが速い
楽譜を見たときに、すぐに「ドレミ」に置き換えられるので、
譜読みがスムーズ。
何度も繰り返すうちに「あれ、もう弾けちゃった!」と
子ども自身も達成感を味わいやすく、
練習のモチベーションにつながります。
合奏やアンサンブルで即対応できる
発表会や学校の合奏で、
周りの音を聴きながら自分の音を合わせられる。
音がズレたときにパッと修正できるので、
周囲から「頼もしいね」と言われることもあります。
ソルフェージュ(聴音・視唱)が得意になる
聴いた音を正確に書き取ったり、
楽譜を声に出して歌ったりする
ソルフェージュの学習でも力を発揮。
専門的な音楽教育に進んだとき、
強みとして活かせる場面が多くなります。
親が期待しすぎると、子どもの可能性を狭めることも
「絶対音感があれば将来安心」──
そう思って、必死に練習させようとする親御さんも少なくありません。
でも、その気持ちが強くなりすぎると、
子どもの世界をかえって小さくしてしまうこともあります。
プレッシャーになってしまう
「あなたには絶対音感が必要」と言われ続けたら、
子どもはどう感じるでしょうか。
“持っていない自分はダメなんだ”という気持ちになってしまい、
音楽そのものが苦しいものに変わってしまうことがあります。
他の力が見えなくなる
音楽には相対音感やリズム感、表現力など、
絶対音感以外にも大切な力がたくさんあります。
ところが親が「絶対音感ばかり」に目を向けてしまうと、
せっかくの子どもの強みを見逃してしまうことにつながります。
「楽しさ」より「成果」になってしまう
子どもが楽しんでピアノに触れているのに、
親が「間違えたらダメ」「今の音、正しく言える?」と
成果ばかりを気にしてしまう…。
そんなやり取りが続けば、最初は大好きだった音楽も、
「やらされるもの」へと変わってしまう危険があります。
絶対音感は“目的”ではなく“ギフト”
絶対音感は、確かに幼少期のほうが身につきやすいと言われています。
だからこそ「小さいうちに訓練させなきゃ」と、
焦る親御さんも少なくありません。
でも──「絶対音感をつけるために音楽を始める」
という考え方は、とても危うい面もあります。
子どもにとって音楽は、本来“好きだから続けるもの”。
それが「結果を出すための手段」になってしまうと、
ちょっとしたつまずきがきっかけで
「もうやめたい」と感じてしまうこともあるのです。
絶対音感は、音楽を長く続ける中で、
自然と育まれていくこともある“恩恵”のひとつ。
「もし身についたらラッキー」くらいの距離感で捉えておいたほうが、
親子にとってもずっと心が軽くなります。
大切なのは、絶対音感をゴールにしないこと。
それは“あとからついてくるギフト”のようなものであり、
目的にしてしまうものではないのです。
親ができるサポートとは
絶対音感を身につけるには、それなりの練習量が必要です。
そして、幼いころから「本物の音楽」に触れる経験もとても大切。
ただし、それを「やらせる」「強いる」形にしてしまうと、
子どもの心はすぐに閉じてしまいます。
親や周りの大人が「練習しなさい」「間違えないで」と強く言いすぎると、
本来は広がっていくはずの可能性が、逆に小さくしぼんでしまうのです。
子どもにとって必要なのは、“強制”ではなく“環境”。
好きな音楽を聴ける時間、自由に音に触れられる空気、
そして自分のペースで練習を重ねられる安心感です。
絶対音感がつくかどうかよりも、
子どもが「音楽って楽しい」「またやりたい」
と思える瞬間を積み重ねていけるかどうか。
その積み重ねこそが、音楽を長く続けていく一番のサポートになります。
“絶対音感をつける”ことに縛られるより、
音楽を楽しむ土台を育てることがサポートになります。
音楽を長く続けるために本当に大切なこと
母は「いやならやめていいよ」という言葉を、
口ぐせのようにいつも言っていました。
それだけ、わたしが積極的に練習していなかったのかもしれません。
親の期待に応えるタイプではなかったのです。
それでも続けてこられたのは、
やっぱり内側に「好き」「表現したい」
という気持ちがあったからだと思います。
一方で、妹は「発表会でかわいい服が着たい」
という目的で習っていましたが、練習が続かず、
舞台に立つ前にやめてしまいました。
同じ家庭で育ち、同じ言葉をかけられても、
結果はまったく違いました。
ここからわかるのは──
音楽を長く続けるかどうかは、外側の目的ではなく、
子どもの内側から湧いてくる動機に大きく左右されるということです。
だから親が本当に大切にしたいのは、
絶対音感の有無や成果を求めることではなく、
「子どもが心から音を好きでいられる状態」を支えること。
それが音楽を長く続けるいちばんの力になります。
まとめ
絶対音感には、確かに「便利さ」や「強み」といえる面があります。
楽譜がなくても弾けたり、曲を覚えるのが速かったり──
親としては魅力的に映るのも当然です。
けれど、その力を“目的”にしてしまうと、
子どもは音楽を「やらされるもの」と感じやすくなり、
可能性を狭めてしまうこともあります。
大切なのは、絶対音感をゴールにしないこと。
それは、音楽を続けるなかで
自然と育まれるかもしれない“ギフト”のような存在です。
そして何より、音楽を長く続けていくために本当に必要なのは、
子どもの内側から湧き出る「好き」「表現したい」という気持ちを守ること。
絶対音感があるかどうかにとらわれず、
親ができることは、子どもが安心して音楽に向き合える環境をそっと支えていくこと。
そのサポートこそが、子どもの未来の音楽を
いちばん豊かにしてくれるのだと思います。
🎵合わせて読みたい記事
🎹第1弾|絶対音感を持つ人のしんどさ
「便利そうに見えるけれど、実は大変な面もあるんだな」と思っていただける記事です。
子どもの可能性を広く見守るために、ぜひ合わせて読んでみてくださいね。
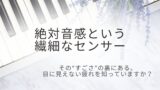
🎹ピアノが上達する子の特徴5つ
上達する子には、絶対音感の有無だけではなく、
ちょっとした共通点があります。
親として知っておくと安心できるヒントをまとめました。