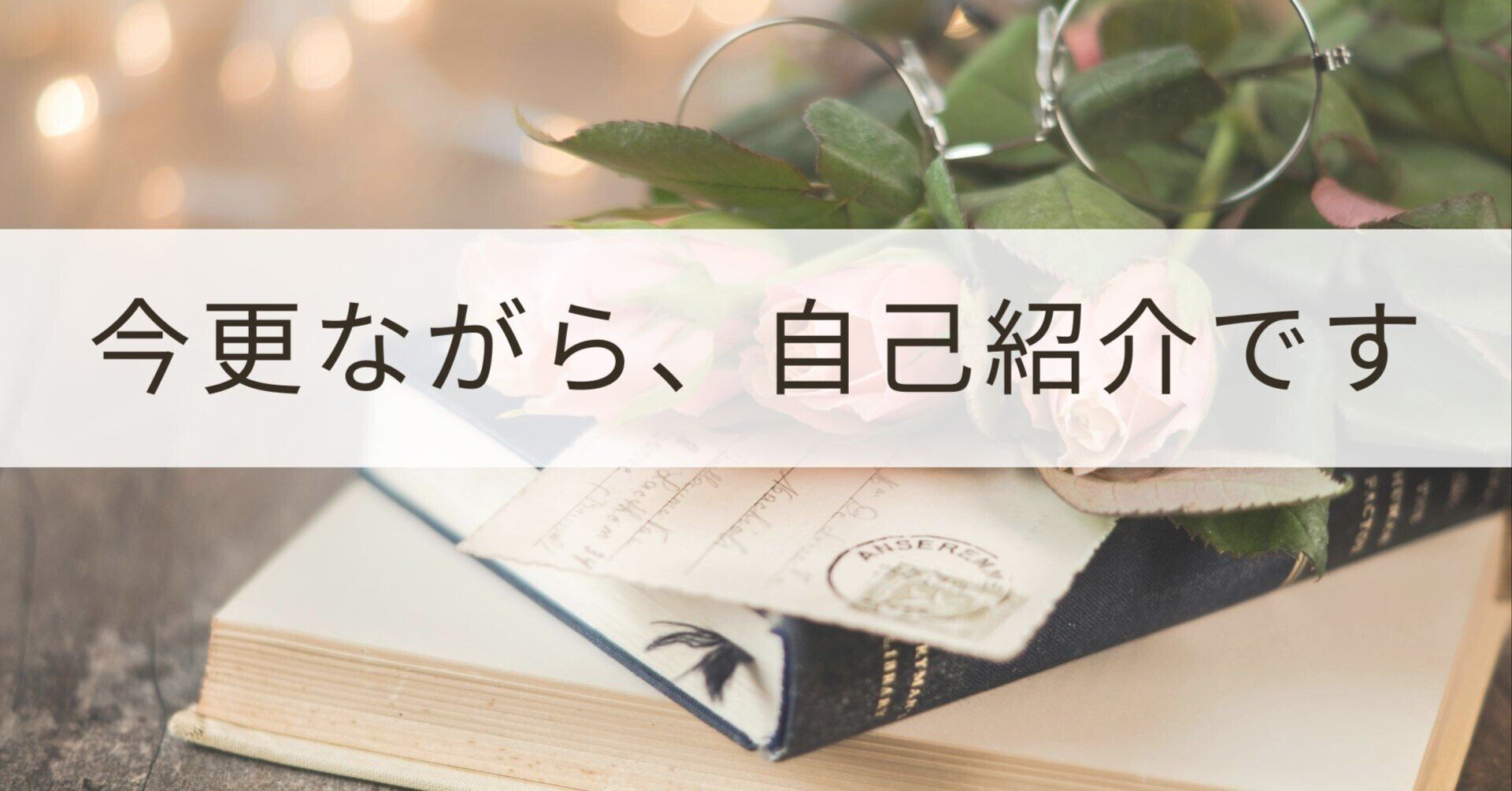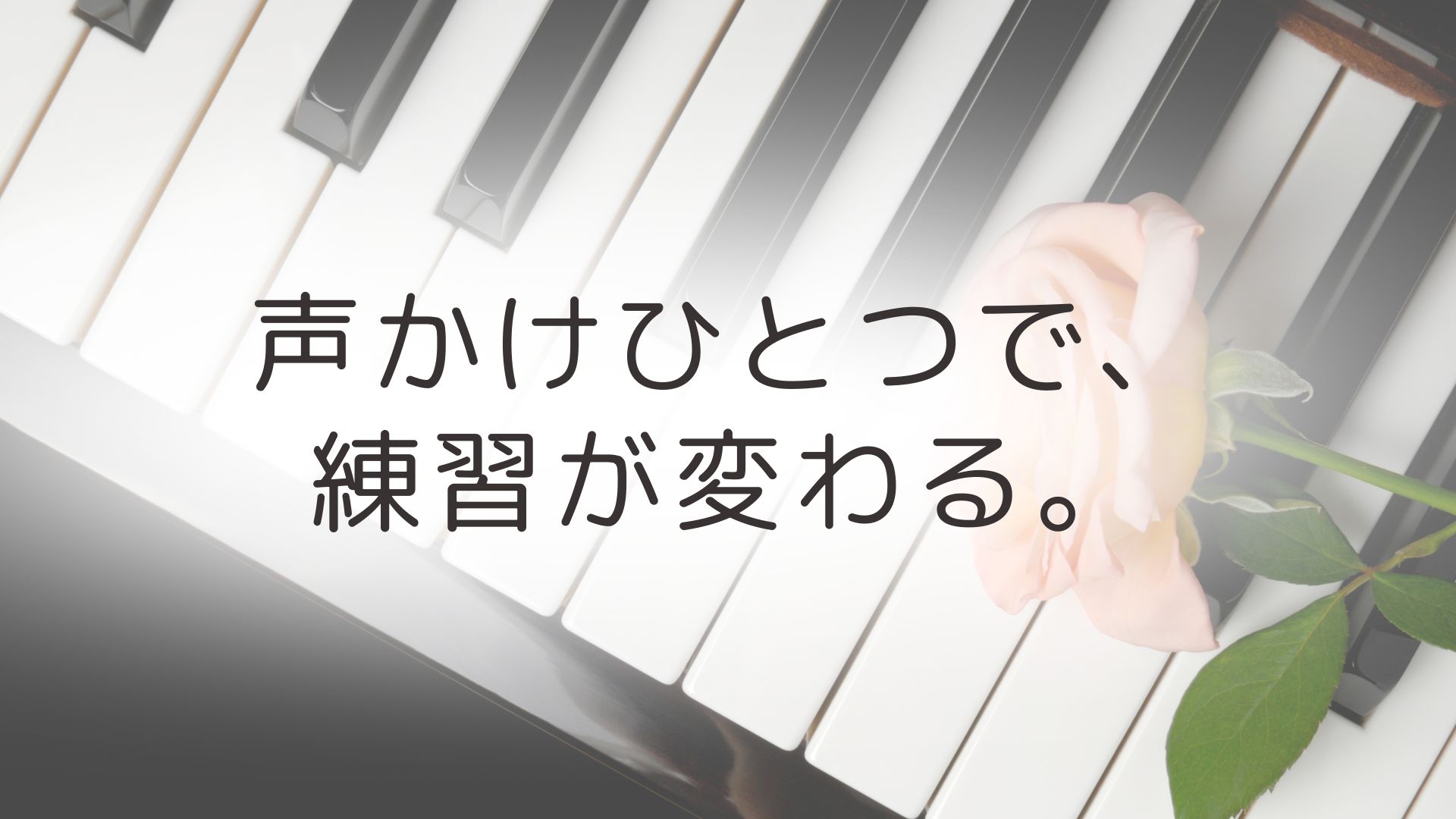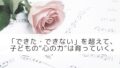ピアノを育てる「自信の芽」
ピアノを教えて25年。
これまで、数えきれないほどの子どもたちと向き合ってきました。
どの子にも共通しているのは、「できない」瞬間に見せる、あの小さな表情です。
くやしさ、あきらめ、そしてもう一度立ち上がろうとする目。
その一瞬にこそ、“自信の芽”が育つ時間があります。
けれど現実には、「何度言ってもできない」
「せっかく練習したのに、うまく弾けない」
そんな姿を見ると、親もつい焦ってしまうものです。
「もっと練習してほしい」「叱るのは愛情だから」
・・・そんな思いの裏には、
“わが子の力を信じたいけれど、
どう支えればいいのか分からない”という、親の迷いが隠れています。
ピアノの練習は、子どもだけでなく、親にとっても“心のレッスン”。
叱らずに伸ばすという関わり方の中に、子どもの自己肯定感を育てるヒントが詰まっています。
今日のテーマは、「できたね」よりも、「見てたよ」。
小さな“声かけ”が、子どもの心にどんな影響を与えるのか・・・
ピアノを通して育つ「自信の芽」を、一緒に見つめていきましょう。
「叱る」と「伝える」は、ちがう
ピアノの練習を見ていると、つい口から出てしまう言葉があります。
「なんでできないの?」
「さっき言ったでしょ?」
その瞬間、子どもは少しだけ肩をすくめ、音が止まります。
「叱る」という行為は、親の“がんばってほしい”という気持ちが形を変えたもの。
でも、子どもの心には「ダメだった自分」が強く残ってしまうのです。
一方で、「伝える」は、目的がちがいます。
叱るのではなく、気持ちを届けること。
「ここ、むずかしいよね」
「もう少しだけ一緒にやってみようか」
こんなふうに“共に向き合う姿勢”で声をかけると、
子どもは“責められている”のではなく“支えられている”と感じます。
脳科学の視点でも、叱られたときの脳は「防御モード」に入り、学習が進みにくくなります。
安心しているときの方が、新しい情報を吸収しやすいことが分かっています。
ピアノも同じ。
「ミスしても大丈夫」という空気の中でこそ、子どもはのびのびと音を出せるのです。
叱るよりも、伝える。
否定ではなく、理解の言葉で関わる。
「できた?」ではなく「どう感じた?」と問いかけてみるだけで、
子どもの心は驚くほど変わっていきます。
「できたね」より、「見てたよ」
子どもがうまく弾けたとき、思わず口にしたくなる言葉があります。
「すごいね!」
「上手にできたね!」
うまくできた瞬間を喜ぶこと自体は、とても自然なことです。
けれど、この“できたね”という言葉の裏には・・・
「できたときだけ価値がある」というメッセージが、
知らず知らずのうちに隠れていることがあります。
ピアノを25年教えてきて感じるのは、
ほんとうに伸びていく子ほど、できない時間を大切にしているということです。
ミスしても、すぐに直さなくていい。
音を外しても、顔を上げてもう一度トライする。
その姿を見ていると、「うまく弾けた」よりもずっと大切な“何か”が育っていることに気づかされます。
そんな子どもたちに、わたしがよくかける言葉があります。
「最後まで弾けたね」ではなく、「今日もよく座ってたね」
「途中でやめなかったね」
この言葉の中に、「あなたを見ていたよ」というメッセージを込めています。
子どもにとって、存在そのものを見守られている安心感は、
“上手にできた”よりも深いところで自信になります。
親御さんにも、ぜひこの魔法の言葉を試してみてください。
たとえば、
「間違えなかったね」よりも「今日は落ち着いて弾けてたね」。
「音をそろえようね」よりも「すごく集中してたね」。
結果よりも“姿勢”や“プロセス”を認める言葉が、
子どもの心の奥に“わたしは大丈夫なんだ”という感覚を残します。
ピアノの音は、「評価の言葉」よりも「見ていたまなざし」によって、
やさしく変わっていきます。
「できたね」より、「見てたよ」。
その一言が、子どもの自己肯定感を静かに育てていくのです。
「がんばり」を共有する時間をつくる
ピアノの上達は、練習量だけで決まるものではありません。
どんな気持ちで弾いたか、どんな音を出したかったか。
その“中身”を一緒に感じ取る時間が、子どもの心を育てます。
レッスンをしていると、「今日は全然できなかった」としょんぼりする子がいます。
でも、少し話を聞いてみると、「昨日より左手が止まらなかった」
「途中で間違えても、最後まで弾けた」
・・・ちゃんと“できたこと”はたくさんあるのです。
子どもはそれを、自分では見つけにくいだけ。
だからこそ、大人が一緒に見つけてあげる時間が大切です。
練習のあと、ほんの1分でもかまいません。
親子で“ふりかえりタイム”を持ってみましょう。
「今日、どんな音が出せた?」
「どこがむずかしかった?」
「どうやってがんばった?」
問いかけの目的は、正解を引き出すことではなく、
子どもが自分の努力を言葉にできるようにすること。
「失敗」も「発見」も、自分の中で整理できた瞬間に、
心の中で“前に進む力”に変わります。
この時間は、子どもにとっても“安心のリセット”になります。
「間違えても、ちゃんと話せば大丈夫」
「聞いてもらえる場所がある」
そんな経験が、子どもの中に“がんばっても大丈夫”という自己信頼を育てていくのです。
ピアノは音を奏でるだけでなく、親子の対話を生み出すきっかけにもなります。
忙しい日々の中で、一緒に笑ったり、考えたりする時間があるだけで、
ピアノの音は、ぐんとやわらかくなります。
親の“焦り”をやさしく手放す
子どもを見ていると、「もっとできるはずなのに」と思うことがあるかもしれません。
努力してほしい、上達してほしい・・・
その気持ちは、どの親も同じです。
けれど、焦りの中から出た言葉ほど、子どもの心には“急かされた”感覚として届いてしまいます。
ピアノを教えていると、上達が早い子よりも、
時間をかけて育つ子のほうが、根が深いことに気づきます。
一歩進んで二歩下がるような日々の中で、自分のペースをつかみ、音と向き合う力が育っていく。
上達とは、結果ではなくプロセスを信じる力なのです。
親が「まだできない」に注目すると、子どもも「自分はできない」と感じやすくなります。
でも、親が「今はその途中」と受け止めると、子どもも「いまの自分でいい」と安心できます。
「まだ」には、未来の可能性が含まれています。
焦りを手放して“今”を信じることが、子どもの自己肯定感のいちばん深い根を支えていきます。
そしてもう一つ大切なのは、親自身が、自分を責めないこと。
「また叱ってしまった」
「上手く声をかけられなかった」
そんな日も、あっていいのです。
完璧な親でなくても大丈夫。
大切なのは、“やさしく戻れる場所”を、自分の中に持つこと。
その余白があるだけで、親も子も、次の一歩を出しやすくなります。
ピアノの成長も、心の成長も、直線ではなく、ゆるやかなプロセスの曲線。
今日できなかったことが、数か月後にふと実を結ぶこともあります。
焦らず、比べず、信じて待つ・・・
それが、子どもの“自分を信じる力”を育てる、いちばんやさしいサポートなのです。
まとめ
ピアノは、「できるようにする」ためだけの習いごとではありません。
子どもが音を探りながら成長していくように、親もまた、見守る力を学んでいく時間です。
「叱らず伸ばす」というのは、甘やかすことでも、放っておくことでもありません。
間違えても大丈夫、と思える安心の中で、子どもが自分の力を信じられるように支えること。
その土台に、自己肯定感が根づいていきます。
ピアノの音は、“教える”よりも“信じる”ときに、やわらかく変わります。
親のまなざしが穏やかになると、子どもの音も、どこか優しく、のびのびと響くようになる。
それはきっと、「あなたはそのままで大丈夫」という無言のメッセージが、
音を通して伝わっているから。
焦らず、比べず、見守る。
それだけで、子どもの中に“自分を信じる力”が育っていきます。
ピアノの音が、親と子の心をつなぐ時間でありますように。
🎵あわせて読みたい
👉 『ピアノは“自信の根”を育てるレッスン|「できた・できない」を超えて育つ、子どもの自己肯定感』
…「できた・できない」を超えて、“自分を信じる力”を育てる第1弾。
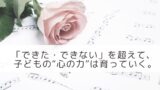
👉 『ピアノは“継続の賜物”。努力よりも、淡々と続ける力。』
…スモールスタートで習慣を育てる3つのポイントを紹介。
歯みがきのように「やるのがあたりまえ」になるまでのプロセスを、やさしく解説しています。

✧✧✧
-1024x576.jpg)
25年以上の指導経験をもとに、
「ピアノと心のつながり」「続ける力」「自己肯定感」など、
学びが“自信”につながるレッスンづくりをテーマに発信しています。
👉 『今更ながら、自己紹介です。(2025年秋・更新)』
(note「One Heart」プロフィールへリンクします)