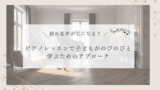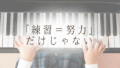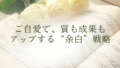子どもの晴れ舞台で、親が試されていること
ピアノ発表会に起こる、子どもと親の“微妙な変化”とは?
ピアノの発表会が近づくと、レッスン室の空気が少し変わります。
子どもたちは緊張と期待が入り混じった表情で、
いつも以上に真剣なまなざしになります。
その姿は、毎年見ていても胸を打たれるものです。
でも・・・
実は、その横で一番ピリピリしているのは、
保護者の方だったりするのです。
この時期になると、「仕上がりが気になるので見学させてください」と
申し出をいただく機会が増えてきます。
もちろん、お子さんのがんばりを応援したい、
というお気持ちはよくわかります。
けれど、見学中に「どうしてそこ間違えるの?」「昨日はできてたのに」
そんなふうに、つい口を挟んでしまう場面も、正直少なくありません。
そのたびに私は、「この空気、きっとおうちでも続いているんだろうな…」と
感じることがあります。
レッスンの時間は、子どもが安心してチャレンジできる場です。
うまくいっても、いかなくても、「自分の力でやってみる」ことが大切。
そこに“評価のまなざし”が入ると、
子どもはいつの間にか、「間違えないように弾くこと」が
目的になってしまうのです。
私は、これまで多くの発表会を見守ってきましたが、
舞台での成功・失敗よりも、
本番に向けて取り組んできた過程こそが、何より尊いと感じています。
そして、それをいちばん近くで見守る立場である親御さんが、
どんなまなざしを向けるかで、
子どもたちの心の育ち方は大きく変わるのです。
なぜ親はピリピリしてしまうのか?〜「いいカッコしぃ」の裏にある感情
ピアノの発表会は、子どもにとっての大きな節目ですが、
実は、親にとっても“見られる日”なのかもしれません。
「ちゃんと弾けるかな」
「うちの子はどう見られるだろう」
「ほかの子より劣って見えないかな」・・・
そんなふうに、心のどこかで周りを意識してしまう気持ち、
私はこれまでの経験から、何度も目にしてきました。
「発表会」というのは、
単に“演奏を披露する場”というだけでなく、
子どもがどんな練習をしてきたか、どんなふうに育ってきたか、
その一端が見える「家庭の縮図」のような場でもあるのです。
だからこそ、無意識のうちに“評価されるのは自分かもしれない”という緊張が、
親御さんにも生まれてしまうのだと思います。
特に、発表会前になると、
「〇〇ちゃん、あの曲すごく仕上がってたね」
「△△くんの衣装、すごく素敵だった」など、
他の親子の様子が自然と耳に入ってくる。
すると、「うちも負けていられない」と、
“いいカッコしぃモード”が発動する。
衣装に力が入りすぎたり、演奏の完成度に神経質になったり、
家での練習が“成果主義”になっていったり・・・
それはすべて、
「わが子をよく見せたい」「がんばっている親でありたい」という、
とても人間らしい、まっすぐな愛情の表れなのです。
けれど、
その気持ちが知らず知らずのうちに強くなりすぎると、
子どもにとっては、“本番”が
「試験」や「審査」のように感じられてしまう。
実際に、レッスン中に
「ママが見てるから、失敗したら怒られる」
「できなかったら恥ずかしい」
と、ぽつりとこぼした子もいました。
私はその言葉に、なんとも言えない胸の痛みを覚えました。
おそらくそのお母さんも、
叱るつもりなどなかったのだと思います。
ただ、「がんばってほしい」という気持ちがあふれて、
それがプレッシャーになってしまった。
このすれ違いは、とてももったいないな・・・と感じます。
こうした場面に立ち会うたび、私はいつも思うのです。
子どもは、親が思う以上に、親の表情や声のトーンに敏感です。
そして、いちばん大事な場面で欲しいのは、「評価」ではなく「信頼」。
「大丈夫。見てるよ」
「失敗しても、あなたはあなた」
そう伝えるだけで、子どもは目の前の舞台に、自分の足で立てるようになります。
発表会の主役は子ども〜失敗よりも大切なこととは?
発表会というと、どうしても「うまく弾けたか」「間違えなかったか」
というところに意識が向きがちです。
けれど、私はいつも思います。
本番に向かって努力してきた日々こそが、子どもにとっての“財産”だと。
曲が難しくて泣いた日。
「もうやりたくない」と言いながら、ピアノに向かってくれた日。
練習の合間に、好きなおやつを食べてリセットした日。
そのひとつひとつが、本番で数分間演奏するという“結果”以上に、
子どもの心の中に残っていくものなのです。
ときどき、こんな場面に出会うことがあります。
舞台の上で、途中で止まってしまった子。
最後まで弾き切れずに、うつむいたまま戻ってくる子。
そんな時、親御さんの表情がこわばっていたり、
帰り道に「どうしてあんなミスしたの?」と問い詰めてしまうこともあるかもしれません。
でも、忘れないでほしいのです。
その子は、その子なりに全力だった。
たとえうまく弾けなかったとしても、
ステージに立っただけでも、大きな一歩だった。
ピアノの舞台にひとりで立つというのは、
大人が思っている以上に勇気のいることです。
照明のまぶしさ、客席の静けさ、指先の感覚、ドキドキする心臓の音・・・
それでも、自分の力で最後までやろうとした、その姿勢こそが、
最大の拍手に値するのです。
失敗して泣いてしまう子がいたら、
「悔しかったね」「よくがんばったね」と、
ただ隣にいてあげてください。
どんな結果でも、「あなたのがんばりを見てたよ」と、
まるごと認める言葉を届けてあげてほしいのです。
子どもにとって、それは一生忘れられない“応援の記憶”になります。
発表会は、たしかに子どもにとって特別な舞台です。
でも、その舞台に立つ前の毎日、積み重ねてきた練習のひとつひとつ、
それをちゃんと見てくれていた人がいる。
信じてくれていた人がいる。
その実感が、子どもにとっていちばんの自信になるのだと思います。
発表会前の関わり方〜子どもの力を引き出す“親のスタンス”とは?
「失敗してもいいから、のびのびやってほしい」
「楽しく弾いてくれたら、それで十分」
そんなふうに思っていたはずなのに・・・
本番が近づくにつれて、
「ちゃんと弾けるかな」「他の子と比べて見劣りしないかな」
といった不安が顔を出しはじめる。
それは決して、間違った気持ちではありません。
むしろ、わが子を想うがゆえに生まれる、ごく自然な感情です。
でも、その不安を子どもに“そのまま”伝えてしまうと、
たとえ言葉にしなくても、子どもはそれを敏感に感じ取ります。
だからこそ、発表会のような節目では、
「信じて見守る」というスタンスが、何よりの支えになります。
子どもが練習に向かう姿を、そっと見ていてあげてください。
うまく弾けなかった時に、手を出すのではなく、
「聴いてるよ」「がんばってるね」と声をかけてあげてください。
緊張しているようなら、
「大丈夫。ミスしても、ちゃんと最後まで聴いてるからね」
そんな一言が、子どもの背中をふっと軽くします。
私はこれまで、
親御さんの“まなざし”ひとつで、
子どもの演奏がぐんと変わる瞬間を、何度も見てきました。
ある生徒さんは、本番直前まで不安そうな表情をしていたのに、
客席に向かって、お母さんがニッコリと笑った瞬間、
ぱっと顔がほころび、堂々とステージに向かって
歩いていったことがありました。
「大丈夫だよ」
その視線が、言葉以上に強く、あたたかく、
子どもにとっての“安心の土台”になるのです。
私たち大人ができることは、子どもが力を発揮できるよう、
心の安全を整えてあげること。
できているところを見つけ、
「よくがんばってるね」と声をかけること。
そして何より、
結果がどうであれ、「あなたを信じてるよ」という姿勢を崩さないこと。
それが、発表会という特別な日に、
子どもに贈ることのできる、最高の応援だと思っています。
実は、親も試されている〜発表会は“見守る覚悟”の時間
ピアノの発表会というと、
どうしても“主役は子ども”と思われがちです。
たしかに、スポットライトの下で演奏するのは子どもたち。
けれど私は、長年この仕事をしてきて思うのです。
舞台裏では、親もまた「自分との勝負」をしているのだと。
「どう見られるか」
「ちゃんと弾けるか」
「親としてどうふるまえばいいか」
そんなふうに、無意識のうちに“周り”を気にしてしまう瞬間。
これは、どんなに優しい親御さんでも、心に浮かんでくるものです。
でもその時、ほんとうに向き合うべき“相手”は、他の誰かではなく、
「自分の内側にある不安」や
「完璧でありたいという願い」なのかもしれません。
わが子を大切に想うからこそ、
「ちゃんとやらせたい」「失敗させたくない」と思ってしまう。
でもその感情の奥には、
「自分は親としてちゃんとできているか」
「誰かに見透かされているんじゃないか」
という、不安や自尊心がひそんでいることもあります。
そして、その感情と静かに向き合いながら、
それでも「この子を信じて見守ろう」と決めること。
それが、親にとっての“本番”なのかもしれません。
私は思います。
ステージに立つのは子どもだけれど、
その日、子どもと一緒に“何かを越える”のは、親も同じ。
だからこそ、
うまくいっても、いかなくても、
子どもが立ち上がったその瞬間を、「共に喜べる自分」でいること。
それが、発表会という日がくれる、
親にとっての、静かな挑戦なのではないでしょうか。
ステージに立つのは子どもだけれど、
舞台裏では、親もまた“自分との勝負”をしているのかもしれません。
その勝負に、完璧な答えはありません。
けれど、少しでも「見守る強さ」に気づけたなら、
親子にとって、それはかけがえのない成長の機会になるはずです。
発表会で伝えたいこと〜子どもを信じる“見守る強さ”
発表会という日は、
子どもにとって特別な体験であると同時に、
親にとっても「自分自身と向き合う時間」なのかもしれません。
わが子の晴れ舞台を前に、
つい口を出したくなるのも、心配になるのも、
それだけ愛しているからこそ。
でも、本当に必要なのは・・・
「正しく導くこと」ではなく、
「信じて待つこと」なのだと思います。
子どもが自分の足でステージに立ち、
その日その瞬間にできる精一杯を表現してくれたなら、
それだけで十分に誇らしい。
うまくいっても、いかなくても、
それをまるごと抱きしめてあげることができたら、
その発表会は、きっと親子にとって忘れられない記憶になるはずです。
ピアノを通して、私がいちばん多く目にしてきたのは、
「できたかどうか」よりも、
「見守られていたかどうか」で、子どもの表情が変わるということ。
信じてもらえた子どもは、強くなります。
たとえ失敗しても、自分の力で立ち上がることができます。
それは、親のまなざしが「評価」ではなく「信頼」だったから。
子どもは、そのまなざしに支えられて、大きくなっていくのです。
だからこそ・・・
どうか、自分自身を信じてほしい。
「ちゃんと見守る力」が、あなたの中にあることを。
誰よりも近くで見てきたあなたが、
子どもを信じていれば、それだけで十分です。
子どもがステージに立つその日、
あなた自身もまた、“親としての強さ”を
育てているのかもしれません。
子どもにとって、そしてあなたにとっても、
発表会が「成長の記念日」になりますように。
♬✧*。合わせて読みたい
本番のミスも、練習のときの“空気”が影響しているかもしれません。
そのヒントは、レッスン見学のときのちょっとした関わり方にあります。
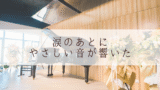
「見守るって、具体的にはどうすればいいの?」という方へ。
レッスン見学の際に親ができること、
やっていいこと・控えた方がいいことをやさしくまとめています。