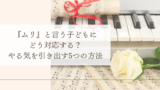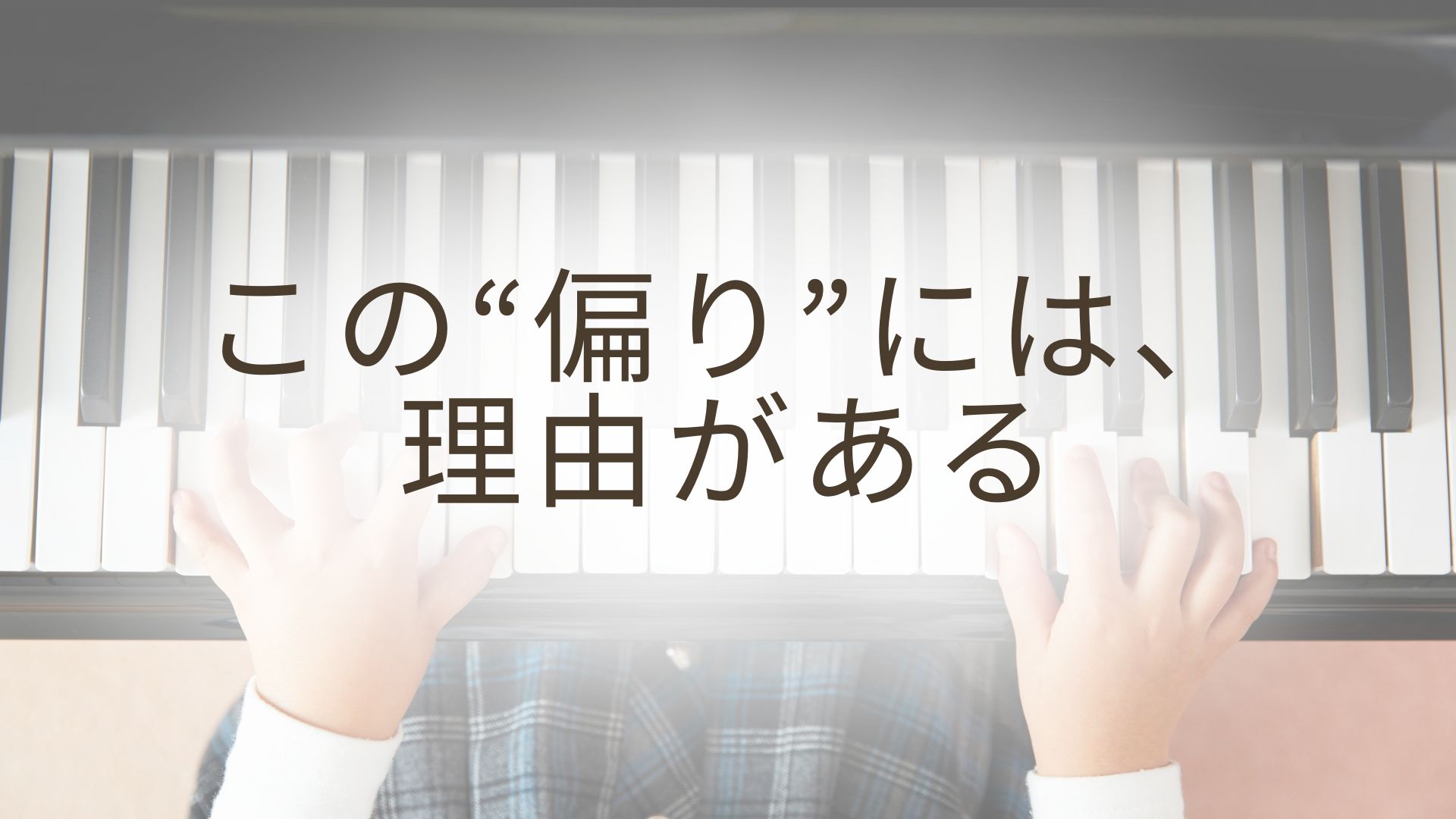「・・・あまり練習できていないんだけど」
レッスンが始まると、彼はいつも、そう言ってそっと椅子に座る。
弾き始めた手元は、思った以上に滑らかで、
Aの部分はよく練習してきた様子が伝わってくる。
音もリズムも、自然な流れがある。
けれど、Bの部分にさしかかった瞬間・・・
「・・・あれ?」
小さくつぶやきながら指が止まり、
少し焦ったような間のあと、何事もなかったかのように先へと進んでいく。
やり直すことも、悔しがることもなく、静かに通り過ぎる。
表情は変わらない。
けれど、その瞬間、部屋の空気がピリッと張りつめたように感じられた。
「ここ、家ではどうだった?」
とたずねると、彼はほんの少し目線を落とし、「うーん」とだけ答える。
毎週、同じ場面、同じやりとりが繰り返された。
できる部分は確実に伸びているのに、
できない部分は、ほとんど変わらない。
何週間かけても、そこだけがずっと取り残されたままだった。
結局、弾けないまま「まる」をつけることになったとき、
わたしの中には少しだけ、引っかかる気持ちが残った。
・・・きっと彼の中では、
あの場所に触れること自体が、少ししんどかったのかもしれない。
♫♫♫
ピアノのレッスンで、「同じところばかり練習してくる」生徒。
できる場所は伸びているのに、なぜか一部分だけ、まったく変わらない・・・
そんな生徒の様子に、思わず首をかしげたことはありませんか?
レッスンの中で、「あれ?」とつぶやいてごまかしながら、
苦手な箇所を静かに通り過ぎていく生徒の姿。
きっと、どの先生にも一度は「あるある」ではないかと思います。
今回は、そんな“練習の偏り”の裏側にある、
子どもたちの心の動きに焦点をあててみたいと思います。
弾けるところばかりを繰り返すのは、安心したいからかもしれない
子どもたちは、つい“弾けるところばかり”を練習してしまうことがあります。
でも、それは「ただラクをしたいから」とは限りません。
ミスが少ない場所を繰り返すのは、
自分にとっての“安全地帯”を確認しているのかもしれません。
「ここは弾ける」「ここなら大丈夫」
そう思える場所があると、練習に取りかかるハードルもぐっと下がります。
そして、何度もそこを弾くことで、
“ちゃんと練習した気がする”という満足感も得られる。
たとえ、進んでいなくても・・・
「できている自分」を感じられることは、子どもにとって大切な心の支えなのです。
成功体験を繰り返して確認し、自分を守っている。
それは、無意識の「セルフコンパッション」なのかもしれません。
難しいところを避けてしまうのは、“できない自分”と向き合う怖さ
できない部分に手をつけようとしない生徒に、
「なんでそこを練習してこなかったの?」と聞きたくなる場面、ありますよね。
でも、そこには、その子なりの“理由”があるのかもしれません。
うまく弾けなかった経験が、
まるで「自分自身がダメ」と言われたように感じてしまった。
そんな過去の感覚が、心のどこかに残っている可能性もあります。
ピアノがうまく弾けなかっただけ・・・
でも、子どもにとっては、
それが自己否定に直結する感覚になってしまうことがあるのです。
だから、「また弾けなかったらどうしよう」「またつまずいたらイヤだな」と思って、
無意識のうちに“その場所”から遠ざかってしまう。
練習していないのではなく、
向き合うのがこわくて、練習できなかったのかもしれません。
それはきっと、「失敗体験の記憶」から自分を守ろうとする、
こころの防衛反応。
もしそうだとしたら、責める前にそっと気づいてあげたいですね。
大人の練習にもみられる「心のクセ」
練習の“偏り”は、子どもだけのものではありません。
ピアノを学んでいるのは、子どもだけではありませんよね。
大人の学習者もまた、「得意なところだけ繰り返して、満足してしまう」ということがあります。
それは決して、怠けているわけでも、やる気がないわけでもありません。
実は、大人こそ・・・できない自分と向き合うのが怖いと感じることがあるのです。
子どもよりも経験を積み、たくさんの「できて当然」
「失敗しちゃいけない」という価値観を背負って生きてきた大人たち。
そんなわたしたちは、うまくできない部分に向き合うことに、
無意識のプレッシャーを感じてしまいやすいのです。
だから、つい得意なところだけをなぞって、
「今日はまあまあ練習したな」と自分を安心させる。
その行動の奥には、「できなさに触れたくない」という、
ごく自然な心の反応があるのかもしれません。
練習の偏り。
それは、単なる“クセ”ではなく、心のクセ。
そしてそれに気づいたとき、私たちは少しずつ変わっていけます。
ピアノの練習は、音楽の上達だけが目的ではありません。
“自分の心”と向き合う時間にもなりうるのです。
年齢によって変わる、練習への向き合い方
同じ「偏った練習」に見えても、
その背景にある心の動きは、年齢や成長段階によって異なることがあります。
幼児期は、「できた!」の感覚を繰り返し味わいたい時期。
成功体験の積み重ねが、そのまま自己肯定感につながります。
多少の偏りがあっても、「弾けた!」を感じられること自体が大切なのです。
小学生になると、少しずつ「苦手」と向き合う力も育ち始めます。
でも、まだまだ失敗には敏感な年ごろ。
指導する側が、安心感を添えてあげることで、苦手な部分にもチャレンジしやすくなります。
中高生は、思春期のまっただなか。
プライドや理想が高まり、失敗体験が強く響いてしまう時期でもあります。
「できない自分」を認めることに大きな勇気が必要なのです。
大人の学習者は、「楽しみたい」「癒されたい」という想いでピアノに向かう方が多く、
ついつい“得意なところ”に気持ちが向きがち。
けれど、だからこそ自分のクセに気づくことで、練習の質が大きく変わることもあります。
年齢や背景によって、
“避けたくなる気持ち”にも“取り組める力”にも違いがあります。
それを知っておくだけで、
生徒さんの姿を、少しやさしいまなざしで見つめられるかもしれません。
まとめ。偏った練習の奥には、“自分を守る心”がある
「同じところばかり練習している」
そんな姿に、つい「サボってるのかな?」
「なんでやらないの?」と感じてしまうこともあるかもしれません。
でも、そこには、その子なりの安心のとり方があるのかもしれません。
弾ける場所を繰り返すのは、自分の中の「できる」を確認して、
自信をつなぎとめようとしていたのかもしれない。
ただし、そのままでは、なかなか成長につながりにくいのも事実です。
だからこそ大切なのは、
偏った練習そのものを否定するのではなく、
その奥にある“心の動き”に、そっと寄り添うこと。
そこから少しずつ、
「できない」にも向き合えるようになる土台が育っていくのだと思います。

🎵合わせて読みたい記事
1.ピアノの上達が“遅い”と感じるときに大切なこと
〜親の不安と、講師との上手なつきあい方
「なんでうちの子、あまり進まないんだろう…?」
ピアノの上達がゆっくりに見えるとき、
親として不安になることもありますよね。
この子なりのペースを大切にしながら、
講師とのやさしいコミュニケーションを築くヒントをまとめました。
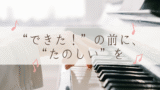
2.『ムリ』と言う子どもにどう対応する?
〜やる気を引き出す5つの方法
「ムリ!できない!」
そう言って、チャレンジを止めてしまう子どもには、
心のブレーキがかかっているのかもしれません。
無理に押し出すのではなく、
内側から“やってみよう”と引き出す関わり方についてご紹介しています。