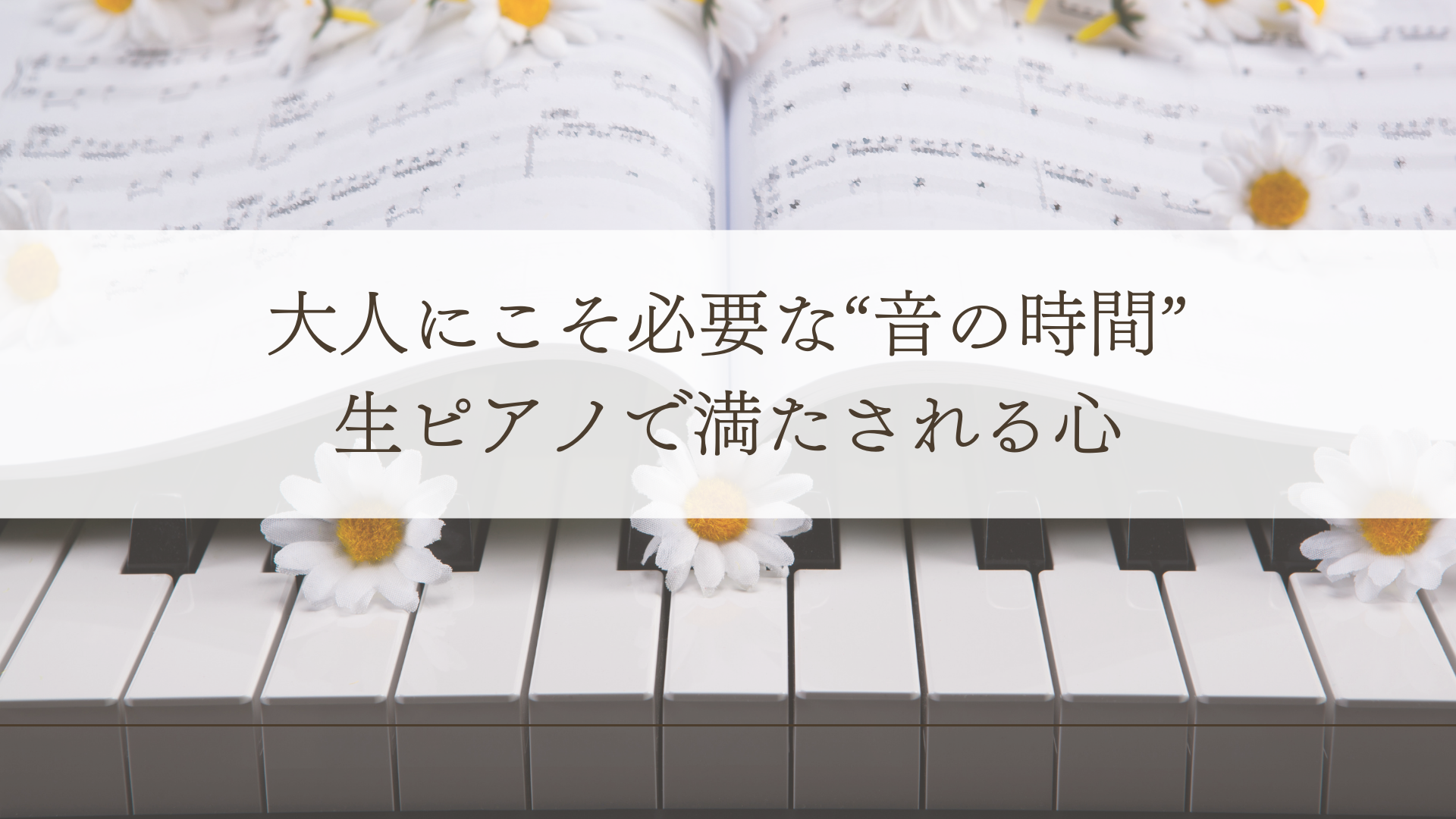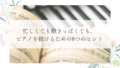ヤマハ音楽教室講師歴25年以上の経験を持つピアノ講師が悩みに寄り添います。
大人にこそ必要な“音の時間”。生ピアノで満たされる心
忙しさに追われて、心の余白がなくなってしまいがちな毎日。
そんな日常のなかで、ピアノの音がふっと心に染み込んでくる瞬間があります。
それは、大人の生徒さんが「なんだか気分がとてもいいです」とレッスンのあとにつぶやいた、
何気ないひとことにあらわれていました。
言葉にしにくいけれど、たしかに存在している“音の癒し”。
今日は「大人にこそ必要な“音の時間”」についてお話ししたいと思います。
“生の響き”が与える、五感への静かな刺激
電子音ではなく、生のピアノの音。
それは空気を震わせ、身体全体に微細に響きます。
耳で聴くだけでなく、指先や皮膚を通じて“感じる”音。
その響きは、心拍や呼吸にそっと寄り添い、
知らず知らずのうちに緊張をゆるめてくれます。
実際、音楽療法の分野でも「一定のテンポや柔らかい音色が副交感神経を優位にし、
リラックス効果をもたらす」という報告があります。
たとえば、ゆったりとしたテンポの音楽を聴くと、
脳波がα波(アルファ波)に変わるとされ、これによりストレスが緩和されたり、
集中力が高まったりするといった研究結果も出ています。
また、ピアノを弾くという行為そのものが「手を動かすことで脳が活性化される」
「リズム運動によってセロトニンが分泌される」など、
心身両方によい影響を与えると言われています。
ピアノのやわらかな低音、やさしい高音。
それらが身体に伝わるとき、わたしたちは言葉を介さずに、
深いところで「ほっ」と息をつけるのです。
注目したいのは、ピアノの音色にも自然界と同じ“1/fゆらぎ”が含まれているという点です。
1/fゆらぎとは、自然の音(小川のせせらぎ、風の音、雨音など)にも見られるリズムのことで、
わたしたちの脳波や心拍に心地よく共鳴し、リラックスを促すことが知られています。
このリズムがあると、脳内のα波が増加し、自律神経のバランスが整うとも言われています。
ピアノの音もまた、そうした「自然のゆらぎ」に似た特性を持っているため、
無意識のうちにわたしたちの神経系に働きかけ、安心感や穏やかさをもたらすのです。
つまり、ピアノの“生の響き”は単なる音以上のもので、わたしたちの内側にある緊張や不安にやさしく寄り添い、心と身体の調律をしてくれているとも言えるのではないでしょうか。
「ただ奏でる」ことで満たされる
大人になると、目的や成果が優先されがち。
でも、ピアノを弾く時間は「うまく弾く」ためだけのものではありません。
たとえ間違えても、指が止まっても、
「今この音を奏でている」という感覚が、自分をふたたび“今ここ”に戻してくれます。
生徒さんのなかには、「演奏のあと、すごく気分がよくなるんです」
「ピアノを弾くと、心が整う感じがする」と言ってくださる方もいます。
もちろん、「うまくなりたい」「もっと上達したい」と思う気持ちも大切です。
ですが、その気持ちが強くなりすぎると、「できていない自分」を責めたり、
音を出すこと自体が楽しくなくなってしまうこともあります。
ピアノは、考え過ぎたときほど指が動かなくなったり、緊張してしまうもの。
だからこそ、ふと肩の力を抜いて「音を楽しむ」ことを忘れないでいたいですね。
「こうあるべき」から解放され、自分と静かに向き合う時間・・・
それが、ほんとうの意味で心を満たすピアノの時間になるのだと思います。
心に余白を——音がくれるやさしい時間
ピアノの生の響きは、忙しい日常のなかで立ち止まるきっかけをくれます。
静かに音を聴くこと。
自分の手で音を奏でてみること。
どちらも、わたしたちの心に静けさと豊かさをもたらしてくれます。
「音の時間」は、何かを成し遂げるための“努力の時間”ではありません。
それは、自分を感じるための“癒しの時間”。
がんばることと、手放すこと。
どちらも音楽の中に共存していて、そのバランスこそが大人にとっての“音の豊かさ”なのかもしれません。
大人にこそ必要な、そんなやさしい音との対話を、これからも大切にしていきたいと思います。