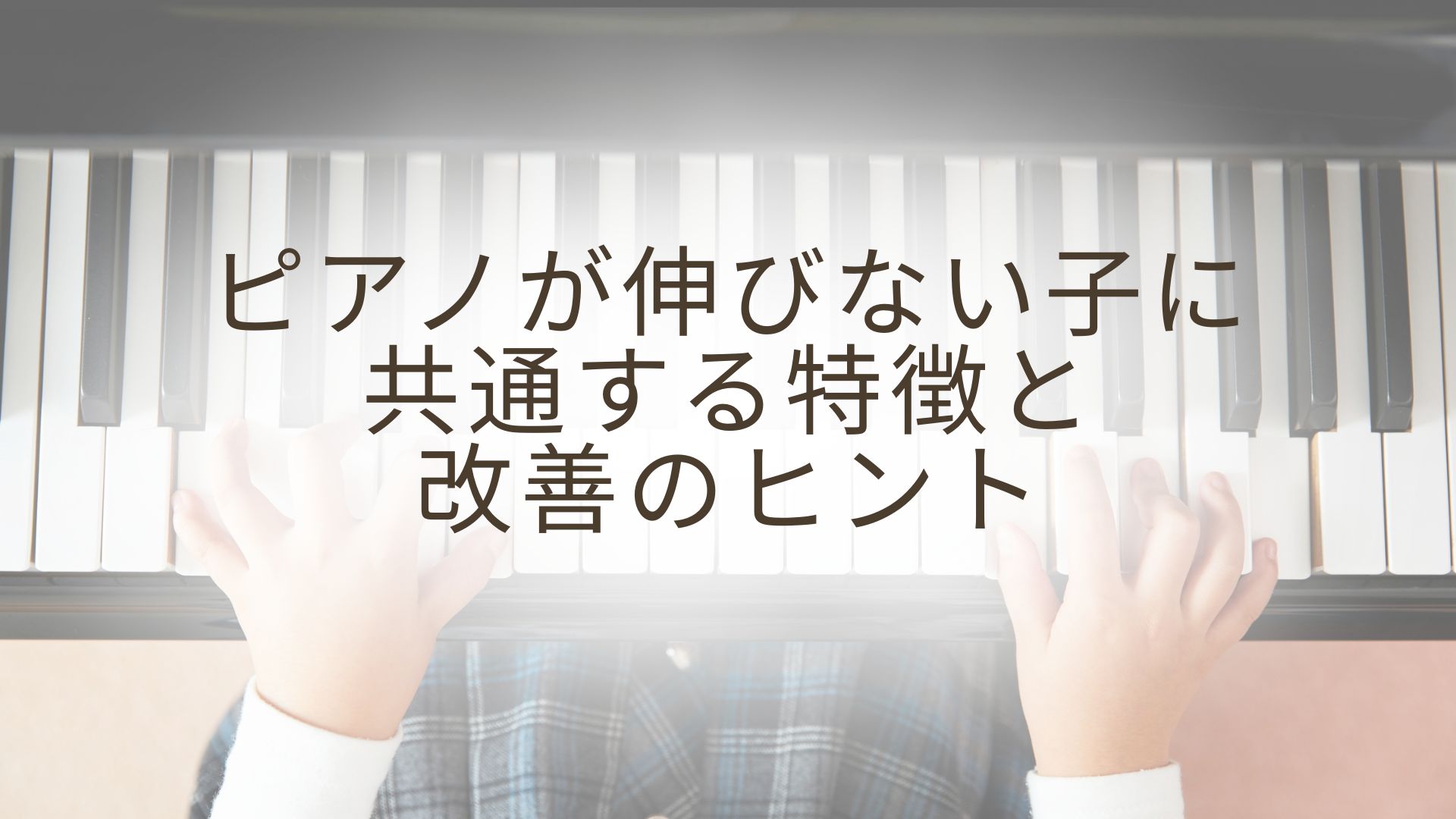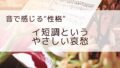子どものピアノが伸びないときに考えたいこと
子どものピアノが「なかなか伸びない」と感じて、
不安になる親御さんは少なくありません。
「毎日練習しているのに…」
「同じ時期に始めた子と比べると遅いのでは?」──
そんな思いを抱くと、
つい子どもを責めたり、焦りが募ってしまうこともあります。
わたし自身、ピアノ講師として25年以上、
多くの子どもたちを指導してきました。
その中で実感しているのは、
「伸びない時期」があるのは自然なこと だということです。
実際に、ぐんと上達する子でも、
その前には停滞しているように見える時期を必ず経験しています。
この記事では、ピアノが伸びない子に見られる特徴や、
その背景にある心理、
そして親や先生ができるサポートについて解説していきます。
今は伸び悩んでいるように見えても、
ちょっとした工夫と関わり方で大きな成長につながることがあるんです。
ピアノが伸びない子に見られる特徴
「どうしてうちの子は伸びないんだろう…?」
そう感じるときには、いくつかの共通した特徴が見られることがあります。
もちろん子どもによって違いますが、
よくあるパターンを整理してみましょう。
練習量が少ない/バラつきがある
ピアノは“積み重ねの習い事”。
毎日10分でもコツコツ続ける子と、
週末にまとめて練習する子では、
どうしても定着に差が出てきます。
「今日は少しだけ」「明日は多めに」など日ごとにバラつきがあると、
忘れてしまうことも多く、なかなか上達を実感しにくくなります。
練習の質が低い(惰性・間違いの繰り返し)
ただ鍵盤に触っているだけだと、上達につながりにくいもの。
間違えたまま何度も繰り返すと、
それが“クセ”になってしまいます。
短い時間でも、部分ごとに区切ったり、
ゆっくり確かめながら弾くと効果的です。
👉“同じところばかり練習してしまう生徒”については、
こちらの記事で具体的にご紹介しています。

集中力が続かない/練習より遊びを優先
子どもにとって、10分間座ってピアノと向き合うことは大きなチャレンジ。
「遊びたい」「テレビを見たい」と
気が散ってしまうのも自然なことです。
そんなときは、練習を細かく分けたり、
ゲーム感覚を取り入れる工夫が役立ちます。
👉 “子どもが集中できない時に。見直したい3つのこと”
については、こちらをご覧ください。
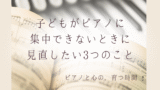
教材や指導法が合っていない
「この曲むずかしい」「つまらない」と感じてしまうと、
練習に身が入りません。
教材そのものや先生との相性も、
やる気に大きく影響します。
子どもの成長段階や興味に合った教材を使うことで、
「弾きたい!」という気持ちを引き出すことができます。
心理的な背景
「ピアノが伸びない子」といっても、
単に練習不足や教材の問題だけではなく、
子どもの“心の状態”が深く関わっていることもあります。
心理的な背景を知ることで、子どもの見方がぐっと変わるはずです。
完璧主義で「失敗したくない」気持ちが強い
一見まじめで頑張り屋さんに見える子ほど、
「間違えたらどうしよう」と強く感じています。
その気持ちが大きいと、弾く前から緊張してしまい、
思うように力を発揮できません。
「間違えても大丈夫」「失敗はチャレンジの証だよ」と
伝えてあげることで、少しずつ心がほどけていきます。
自信がなく挑戦を避ける
「どうせできないから」と、
新しい曲やむずかしい部分にチャレンジするのを避ける子もいます。
これは「できなかった経験」が積み重なって、
自分に自信を持てなくなっているサインです。
小さな成功体験を積ませてあげることで、
「やってみようかな」という気持ちが芽生えやすくなります。
「ここまで弾けたね」と具体的に認める声かけが効果的です。
親や先生の期待に萎縮している
「もっと練習してね」「次の発表会はこの曲を」といった言葉が、
子どもにとってプレッシャーになることも。
期待が大きすぎると、「応えられないとダメなんだ」と感じてしまい、
ピアノへの意欲そのものがしぼんでしまいます。
もちろん期待する気持ちは自然なことですが、
子どもが「応援してもらえている」と感じられる言葉の方が、
やる気につながりやすいです。
伸びる子との違い(比較視点)
「伸びない子」に共通する特徴がある一方で、
ぐんぐん力を伸ばしていく子にも、いくつかの共通点があります。
才能やセンスよりも、
日々の姿勢や周りの環境が大きなカギになっています。
練習を楽しむ姿勢
伸びる子は、練習そのものを「やらされている時間」と感じていません。
「今日はどこまで弾けるかな?」
「このフレーズ、昨日よりきれいに弾きたい!」と、
小さなワクワクを見つけながら取り組んでいます。
もちろん、気が進まない日もありますが、
練習が“義務”ではなく“遊びやチャレンジ”に近い感覚を持っていることが大きな違いです。
小さな目標設定ができている
「1ページ全部を弾けるように」ではなく、
「今日は2段だけを止まらずに弾こう」といった、
小さな目標を立てられる子は伸びやすいです。
達成できたときの喜びが積み重なり、
「できた!」「次もやってみよう!」というポジティブな循環が生まれます。
このサイクルは、親や先生が一緒に目標を区切ってあげることで作ることもできます。
周囲からの声かけ・サポートが前向き
子ども自身の努力だけでなく、
周りの環境も大きな影響を与えます。
「まだできてないね」よりも「ここまで弾けるようになったね」と、
できた部分を認めてもらえると、子どもは安心して挑戦できます。
また、親や先生が「結果」よりも「過程」に注目して声をかけると、
子どもの心はプレッシャーから解放されます。
周囲のマインドが「評価する立場」ではなく
「一緒に育てていく仲間」という姿勢に変わると、
子どもの伸び方も大きく変わります。
親・先生ができる改善のヒント
「伸びない子」には共通する特徴がありましたが、
そこから抜け出すためのサポート方法もちゃんとあります。
大切なのは「叱って直す」よりも「工夫して支える」視点。
ここでは、家庭やレッスンでできる具体的なヒントをご紹介します。
練習を細かく分けて「できた!」を積ませる
1曲を通すことだけを目標にすると、
できない部分にばかり目が行きがちです。
「今日は右手だけ」「この2小節だけ」と小さく区切って練習すると、
達成感を味わいやすくなります。
「ここまで弾けた!」という体験を積み重ねることで、
やる気の芽が育っていきます。
声かけで「努力」を認める(できない→できたの変化に注目)
「まだできてないね」と結果を指摘するよりも、
努力のプロセスに注目してあげることが大切です。
「昨日よりスムーズになったね」「ゆっくり弾けるようになったね」と、
小さな変化を言葉にして伝えると、子どもは自分の成長を実感できます。
こうした声かけの工夫は、
長期的に子どものモチベーションを保つ大きな支えになります。
子どもに合った教材・環境に変えてみる
「難しすぎてイヤ」「簡単すぎてつまらない」という状態は、
意欲を下げる原因になります。
今のレベルや興味に合った教材に変えるだけでも、
取り組む姿勢がガラッと変わることがあります。
また、練習環境も意外と大切です。
ピアノを置く場所、照明の明るさ、
周囲の雑音などが快適だと、子どもは自然とピアノに向かいやすくなります。
ピアノを置く場所については、
「どこで練習させるのがいいの?」と迷う親御さんも多いと思います。
👉詳しくはこちらの記事で解説しています。
【ピアノ講師が本音で解説】リビング練習vs個室練習、どちらが上達する?
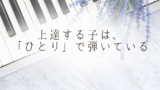
練習がイヤにならないしくみをつくる
「練習しなさい!」の声かけが増えると、
どうしてもピアノが義務になりがちです。
1日10分タイマーを使ったり、練習したらシールを貼るなど、
遊び心を取り入れると負担が減ります。
ゲーム感覚で「今日はクリアできるかな?」と感じられる工夫は、
練習を継続させる大きな味方になります。
まとめ
ピアノが「伸びない」と感じるとき、
つい「うちの子は才能がないのでは…」と不安になるかもしれません。
けれど、伸びるスピードにはそれぞれのペースがあり、
停滞しているように見える時期も大切な成長のプロセスです。
むしろ、思うようにいかない時期こそが「考える力」や「続ける力」を育てています。
目に見える結果はすぐに出なくても、
心や感性の部分では確実に前進しています。
親御さんにできる一番のサポートは、
焦らずに「一緒に音楽を楽しむ」こと。
子どもが弾く音を「いいね」と受け止めたり、
親子で一緒に口ずさんだりするだけでも、
ピアノはもっと身近であたたかいものになります。
「伸びない=才能がない」ではありません。
その子のペースで、音楽を楽しみながら続けていくことが、
なにより大きな力につながります。
🎵あわせて読みたい記事
【比較で理解が深まる記事】
👉 ピアノが伸びる子の特徴。
ピアノが上達する子の特徴5つ
【練習の悩みを解決するヒント】
👉 同じところばかり練習してしまうときに。
ピアノ練習の“偏り”に隠れた心の動き
👉 子どもが集中できない時に。
子どもが集中できないとき。見直したい3つのこと。
【親のサポートに役立つ記事】
👉 「うちの子、練習しないんです」
その言葉の奥にはもっと深いものがあるんです。
「うちの子、練習しないんです」。その言葉の奥にあるもの
👉 「練習しなさい」と言っても、効果がないときありますよね。
そんなとき、どう向き合うかを書いています。
家でピアノの練習をしない子どもにどう向き合う?